※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、プロモーションが含まれています

「ASDなそら」管理人のそらです。
ASD(自閉スペクトラム症)当事者の視点で、
仕事・生活に役立つ情報を発信しています(^^)
就職活動・転職活動において、
面接官から必ずといっていいほど聞かれる質問があります。
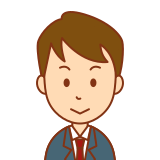
あなたの強みはなんですか?
一見シンプルですが、答えるのは簡単ではありません。
特に発達障がい・精神疾患のある方にとっては、
「強みなんてない」「弱みばかり思い浮かぶ」と感じることが少なくありません。
さらに、障がい者雇用の場面では次のように聞かれることもあります。
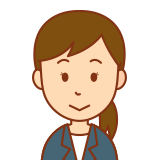
あなたが配慮を求めること(=弱み)はなんですか?
これは単に「できないこと」を確認したいわけではなく、
次の点を知るための質問です。
- あなたが「どうすれば能力を発揮しやすい」のか
- 「どのようなサポートがあれば」活躍できるのか
つまり「強み」と「弱み」は、就職活動において自分を理解し、
相手に伝えるための大切な材料なのです。
- 「強み」「弱み」とはなにか
- 「強み」「弱み」を知る方法、工夫
- 「強み」「弱み」がもたらすメリット
なぜ面接官は「強み」と「弱み」を知りたいのか
面接官が「強み」「弱み」を聞く背景には、いくつかの理由があります。
1つずつ見ていきましょう。
- 仕事との「マッチングを確認する」ため
- 「配慮の必要性」を把握するため
- 「自己理解度を確認」するため
① 仕事との「マッチングを確認する」ため
企業は応募者に「即戦力」だけを求めているわけではありません。
むしろ障がい者雇用では
「長く / 安心して / 働き続けてもらえるか」どうかが重視されます。

(管理人)
私の経験から、就労移行支援では、
「仕事の適正度以上に」それを重要視している、と感じます。
そのため「どんな環境で強みを活かせるのか」「どんな場面で弱みが出やすいのか」
これらを知ることで、適切な配置・業務内容を検討してもらえます。
② 「配慮の必要性」を把握するため
「弱み」を聞かれるのは、単に欠点を知りたいからではなく
「配慮が必要な部分」を明確にするためです。
静かな環境では、集中できる
➡️ 机の配置など、工夫することができる
③ 「自己理解度を確認」するため
面接官は「自己理解ができているか」を重要視します。
「過集中になると、疲れが一気にたまりやすい」を例に見てみましょう。
過集中になると、疲れが一気にたまりやすい
➡️ ならないように、対策を立てられる
➡️ 疲れがたまってしまう場合、業務そのものをしない選択肢も生まれる
安定して、長く働ける可能性が高い
過集中になると、疲れが一気にたまりやすい
➡️ 働きながら、必要な調整を行えない
➡️ 入社しても身体・心がついていかない
休みがちになってしまう・・・


「強み」とは何か
「強み」と聞くと、
特別な才能・高度なスキルを思い浮かべる人が多いかもしれません。
しかし、強みは必ずしも「特別」なものである必要はありません。
- 疲れずに続けられること
- 人から「助かる」と言われたこと
- 自分では当たり前だが、他人から褒められること
これらすべてが強みになりえます
「ルールを守るのが得意」とする
- 毎日同じ手順を、正しく実行できる
- 業務の安定性を支えてくれる

「弱み」とは何か
弱みというと「欠点」「短所」と感じてしまいがちですが、
本来の意味は少し違います。
弱みは「苦手な部分」であり「支援・工夫が必要な部分」です。
- 曖昧な指示に、対応しづらい
- 長時間の作業で、疲れやすい
- 音・光に敏感で、集中できない
これらは「できない」ではなく、
「条件を整える必要がある」というだけのことです。
「弱みを理解し、言葉にして伝えることができる」と、
「あなたも」「上司も」安心して働くことができます。

(管理人)
ただし、配慮をしてもらうのは
「業務に影響が出る」ものに限定しましよう。
あれもこれも、となってしまうと
上司の負担が大きくなりすぎてしまいます。
「強み」と「弱み」を知る「3つの方法」
- 「他者のフィードバック」をもらう
- 「自己観察」をする
- 「過去の経験を分析」する
上から順番に見ていきましょう。
① 「他者のフィードバック」をもらう
家族・友人、支援者、職場の上司など、受けた言葉を振り返ってみましょう。
- 「丁寧だね」と言われた
- 「声が聞き取りやすい」と褒められた
- 「疲れやすいね」と指摘された
こうした言葉は、自分では気づきにくい特性を教えてくれます。

(管理人)
私はこれが「長所」「短所」を知る一番の方法だと思います。
他人を頼ることを学べ、長く働けるきっかけになります。
② 「自己観察」をする
日常の中で「どんな作業が楽か」「どんな場面で疲れるか」を
観察してみましょう。
- 単純作業は集中できる
- 臨機応変な対応は苦手
- 静かな環境だと、パフォーマンスが上がる
こうした観察結果は、面接で具体的に伝える材料になります。

(管理人)
詳しい方法は、後ほど紹介します。
③ 「過去の経験を分析」する
学校生活・趣味の活動を振り返ると、自分の特性が見えてくることがあります。
- 図工で「丁寧に仕上げる」と評価された ➡️ 正確性の強み
- 作文で「表現力がある」と言われた ➡️ 言語化の強み
過去に自然とできていたことは、
今の強みにつながっていることが多いのです。

(管理人)
「通知表」「アルバム」「卒業文集」
これらなどが手元にある方は、ぜひ確認してみてください。
- 幼稚園まで
- 小学校
- 中学校
- 高校
- 鋭意執筆中・・・
- 大学
- 鋭意執筆中・・・
「強み」と「弱み」は表裏一体
多くの場合、強み・弱みは表裏一体です。
- 集中力がある ⇔ 過集中で疲れやすい
- 丁寧に作業できる ⇔ スピードが遅い
- マイペースで冷静 ⇔ 協調性が乏しいと見られる
つまり、強みの裏には弱みが隠れており、
その逆(弱みをひっくり返せば、強みである)も成り立ちます。
大切なのは「自分が活躍できる条件」を明確にし、
それを周囲に説明できるようにすることです。

(管理人)
直接面と向かって、でなくても、
「文字にできる」ことが非常に大きいのです。
具体的な「強みのパターン」
強みには、さまざまな種類があります。
- 正確性
- 間違うことなく、作業できる
- 集中力
- 単純作業を続けられる
- ルール遵守
- 決められた手順に、安心感を持てる
- PCスキル
- Excel / Word / PowerPointなどの操作が得意
- 声、態度
- はっきりした発声
- 落ち着いた対応ができる
具体的な「弱みのパターン」
同様に、弱みも多種多彩です。
- 過集中
- 気づかずに疲れてしまう
- 曖昧さに弱い
- 指示が抽象的だと混乱する
- 疲れやすさ
- 体力が長く保たない
- 感覚過敏
- 音/光/においに敏感
- マルチタスクの困難
- 複数の作業を同時に進めにくい
「強み」と「弱み」を「言語化する」方法
- 気づく
- 自己観察 ➡️ 分析する
- 支援者、上司などからのフィードバックで把握する
- 客観的な意見をもらう
- 検査なども参考にする
- 例;WAIS検査、職業適性テスト
- 整理する
- ノート/表にまとめる
- 毎日の調子、作業のしやすさを書き残す
- 日記にまとめるのも⭕️
- ノート/表にまとめる
- 伝える
- 面接、面談などでシンプルに言葉にする
- 上記が難しい場合;文字にして伝える
「面接で伝える」ときの工夫
- 強みと弱みをセットで伝える
- 「活躍条件」を一緒に話す
- ネガティブ表現を避ける
集中力は誰よりもあります。
ただし過集中になりやすいので、昼休憩とは別に、
軽い休息を取りながら働けると助かります。
このように伝えると、相手の理解が確実にが深まります
「強み」「弱み」の整理がもたらす「メリット」
- 面接での自己PRがしやすくなる
- 無理のない働き方を選べる
- 自己肯定感が高まる
- 周囲の理解が進む

(管理人)
「働く」のみならず、「生きやすくなる」ことも大きなポイントです。
おわりに:強み・弱みは「誰もが持っている」
強み・弱みは、特別な才能・欠点ではありません。
「疲れずにできること」「他人から感謝されたこと」こそが強みです。
そして弱みは、自分を守るために必要な「条件のヒント」です。
強み・弱みを言語化することは、発達障がい・精神疾患のある方に限らず、
すべての人に役立つ自己理解の手段です。
今は「自分のことがよく分からない」と思っていても、
少しずつ整理していけば、面接だけでなく人生全体が生きやすくなっていきます。
「この記事だけでは、イメージしにくい…」
そんなあなたは「私の実例を元に」探してみてください。

(管理人)



コメント