
「ASDなそら」管理人のそらです。
ASD(自閉スペクトラム症)当事者の視点で、
仕事・生活に役立つ情報を発信しています(^^)
神経発達症(ASD、ADHDなど)を持つ私たちは、
日常生活の中でさまざまなストレスにさらされやすい傾向があります。
- ちょっとした環境の変化
- 人間関係
- 音や光
- 予定変更 など
「些細なこと」と言われがちな刺激でも、
心が大きく揺れてしまうことがあります。

しかし、「だからダメ」ではありません。
自分の特性を理解し、適切なケア方法を身につけることで、
心の健康を守りながら、穏やかに日々を過ごすことは十分可能です。
この記事では、私自身の経験をもとに、
ASD当事者が実際に取り組めるメンタルケアの方法を紹介します。
無理のないペースで、
少しずつ「自分を大切にする方法」を見つけていきましょう。
自己理解から始めるメンタルケア
なぜ自己理解が必要なのか?
ASD当事者は、自責の念にとらわれやすい傾向にあります。
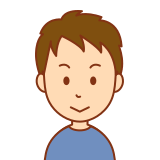
どうして「自分だけ」こう感じるだろう…
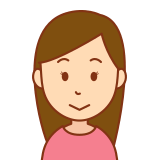
なんで「私だけ」うまくできないだろう…

(管理人)
私自身も
「みんなできているのに、どうして自分だけできないんだろう…」
そう悩んだ時期がありました。
ただ、自分の脳や感覚の仕組みが他の人と違うことを知ってからは、
「これは病気ではなく、特性なんだ」と気づけるようになりました。
自己理解の方法について
① 特性を把握するための日記
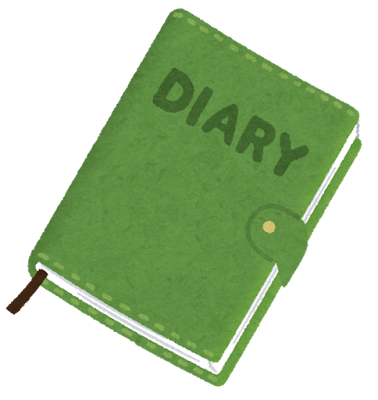
一番のおすすめは、「刺激」と「反応」の記録をつけることです。
- 朝の満員バス
- 頭痛・気分の落ち込み
- 蛍光灯の下での作業
- 目の疲れ・集中力の低下
- 午前中の静かなカフェで作業
- 作業効率アップ
このように「どんな状況で」「どう感じたか」を毎日少しだけ書き留めることで、
無理のない働き方や生活スタイルのヒントが見えてきます。
○日記の書き方について、詳しくはこちらから
○メモの力も侮れません。詳しくはこちらから
② カウンセリングや診断の活用
自分ひとりで抱え込むより、
発達障害に理解のある専門家に相談することで、
客観的なアドバイスを受けることができます。

「特性のせいで生きづらい」のではなく、
「社会の仕組みが合っていないだけ」と気づける機会にもなります。

(管理人)
私も先日、カウンセリングを受けてきました。
自身では「気づくことのできなかったこと」を褒めてくださり、
すごく自信になりました。
感覚過敏へのケア:環境調整をする
ASDの大きな特徴のひとつが「感覚過敏」です。

(管理人)
私も、
特定の音(金属音)や、
頭痛(天気・ストレス)で
体調を崩すことがあります。
- ノイズキャンセリングヘッドホン・耳栓を活用する
- 着心地のよい服(タグのないもの、綿素材)を選ぶ
- ユニクロがおすすめです ➡️ 公式サイトはこちらから
- 間接照明で調節できるようにする
- 昼:白色
- 夜:電球色(温かみのある色)
- 香りがきつい空間
➡️ マスクを活用
感覚刺激をコントロールできるだけで、気分の安定度は大きく変わります。

疲れる前に休む
- 気づいたら疲れきっていた
- 朝は元気だったのに、午後から突然ダウン
ASDの私たちは、集中力の「ON/OFF」が極端になりがちです。
気づかないうちにエネルギーを使い切ってしまい、
あとからドッと疲れが来ることがあります。

(管理人)
私自身、何度も経験しました。
回復まで1週間近くかかりました…
- 1時間に1回、3~5分の休憩をとる
- スマホの「利用時間リマインダー」を活用
- 昼食後、アイマスク+15分の仮眠
- 脳を一度リセット
- 「視線の休憩」を行う
- 窓の外の緑を見るだけでOK
大切なのは「疲れていなくても休む」ことです。
疲労感が出てからでは遅いのです。
あらかじめ「エネルギーを温存する習慣」を身につけましょう。

(管理人)
ASDの特性対策は「先手を打つ」ことが重要です。
後手に回ってしまうと、
元通りになるまでに想像以上の期間を要します。
人間関係のストレスに対処する
ASD当事者にとって、
人との関わりはストレスの温床になりやすいものです。
- 空気を読む
- あいまいな指示に対応する
- 予定変更に巻き込まれる など

- ヘルプマーク・障害者手帳を提示する
- 自分の特性を説明しやすくする
- SNSの通知はOFFにする
- 「自分なりのペースで返信する」のがGOOD
- 疲れる人間関係から、距離をとる
- 「話せる相手」を持つ
- 一人だけでもOK。心の避難所になる
- 主治医以外の居場所もあると、よりよい
人間関係は「全員と仲良くすること」がゴールではありません。
「安心して過ごせる関係性を、少数でも持つ」ことが、
心の安定につながります。

自己肯定感を育てる
失敗や否定的な言葉に、私たちは強く反応してしまいがちです。
でも、それは「傷つきやすい心」があるからこそ。
むしろ、丁寧に生きている証拠でもあります。
- 毎日「今日できたこと」を3つ書き出す
- 小さすぎることでもOK
- 詳しくはこちらから
- 自分に、優しい言葉をかける
- 例:「よくやったね」
「ミスしたけど、どうにでもなるじゃん」など
- 例:「よくやったね」
- 『過去の自分と比べる』
- 他人と比べるのは、精神的に❌️
- 昨日より少しでも前進していればOK

(管理人)
私の場合…
「今日も、無事に出勤できた」
「上司に気持ちを伝えられた」だけで、OKにしています。
自分のペースで「小さな成功体験」を積み重ねましょう。
体を動かす:心をほぐす
ASD当事者は「考えすぎる」「頭が疲れやすい」と感じることがあります。
そんなとき、体を動かすことで思考を止める時間をつくるのが効果的です。
- 起床後・就寝前のストレッチ
- 筋トレもよい
- ゆっくり散歩
- 自宅の近所、公園など
- 軽い水中ウォーキング
- 刺激が少ないのでおすすめ
- 慣れてきたら、泳ぐのもGOOD


(管理人)
「疲れるから動けない」と思うときこそ、
ほんの少しだけでも動くことで、
気持ちが前向きになることがあります。
ただし、疲れが限界を超えている場合、
寝るなど、体力回復に専念しましょう。
達成可能な「小さな目標」を立てる
完璧を目指してしまうと、私たちはすぐに疲れてしまいます。
特にASD傾向がある人は、「0か100か」になりやすいです。

- タイマーをセットする
- 例:10分間だけ作業する など
- 数字で具体的に
- あえて、数量を制限する
- 例:机の上の書類を「3枚だけ」片づける など
- ToDoリストは「できたらOK」方式にする
- 未達成・溜まってきても、自分を責めない
大きな山を一気に登る必要はありません。
「今日は5歩進めた」その事実だけで十分です。
おわりに:無理なく、自分の味方になるケアを
メンタルケアは「特別なこと」ではありません。
私たちが生きやすくなるための、日々の工夫の積み重ねです。
- 全部をやろうとしなくていい
- 1つだけでも試してみれば、それはもう「前進」
- 調子が悪い時は、自分を責めず、休む勇気を持つ
そして何より、
自分ひとりで抱え込まずに、信頼できる人や専門家とつながっていてください。
あなたのことを理解し、寄り添ってくれる人は必ずいます。

(管理人)
自分のペースで、
こつこつ、ぼちぼち、のんびりと。
今日もあなたが、あなたらしくいられる時間が少しでも増えますように。



コメント