※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、プロモーションが含まれています

「ASDなそら」管理人のそらです。
ASD(自閉スペクトラム症)当事者の視点で、
仕事・生活に役立つ情報を発信しています(^^)
「自分の特性・限界を理解する」という言葉を耳にすることは多いですが、
実際にどうやって行えばいいのか、悩む人は少なくありません。
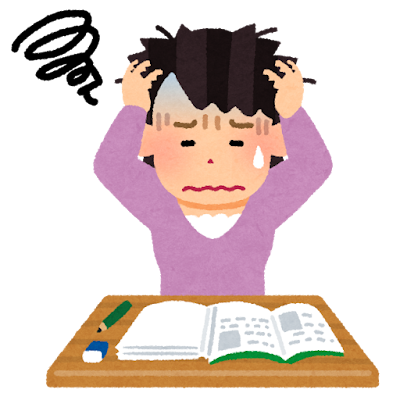
特に「発達障がい」「精神疾患」を抱えている人にとって、
自分の状態を正しく理解することは、
生活の安定・支援の活用につながる重要なステップです。
しかしこの「自己理解」は、
心理テストのように「一度で終わるもの」ではありません。
「日々の積み重ねの中で、生きていく土台を作っていく」ことなのです。
- 毎日生きている中でするもの
- あなた自身の状態を観察する
- あなた一人/他者と一緒に振り返る
- 少しずつ整理していく
この作業は「働く前」「福祉支援を受ける前」からでも始めることができます。
自分の状態を把握しておくことで、
後に福祉サービスを受ける際もスムーズに情報を共有できるようになり、
生活全体を安定させる基礎になります。
- 「一人でもできる」自己理解
- ① 自分を観察する
- ② 得意/不得意を知る
- ③ 限界を知る
- 他人と「より深い自己理解」をする
- ④ 言葉にする
- 「これからのために」できる自己理解
- ⑤ 「障がい者福祉」を理解する
- ⑥ 「見える化」する
- ⑦ 「障がい者福祉を利用する」「前の準備」
①:「自分を観察する」から始める
自己理解の第一歩は「自分を観察する」ことです。

「観察」って、どこか難しそう…

(管理人)
言葉だけでは、そう感じることでしょう。
しかし、やることはとても簡単です。
それは「気になった感覚」を「記録していく」だけです。
観察の目的は「できた・できなかった」を評価することではなく、
自分の状態のパターンを見つけることです。
次のような点を「1日単位で」「軽く」メモしてみましょう。
- 朝起きたときの気分、体調
- 集中できた時間帯
- 疲れを感じたタイミング
- 苦手な場面、人とのやり取り
- 睡眠、天気、食事などの影響
具体的には⬇️
- 「今日は一日を通して、なんとなく疲れた」
- 「今日は〇〇に集中できた」
最初は「なんか疲れた」のように「ざっくりでOK」です。
毎日続けようとすると疲れてしまうので、続けやすい形を選びましょう。
- メモ帳
- 手書きだと、効果↗️
- 日記
- 手書きだと、効果↗️
- スマホアプリでもOK
こうして自分の状態を「見える化」していくことで、
「自分が『どういう条件で』調子を崩しやすいか」が
少しずつわかってきます。
②:「得意」「不得意」を整理してみる
次のステップは「得意」「不得意」を整理することです。
「①:「自分を観察する」から始める」と同じく、
「なんとなく」で構いません。

(管理人)
ここでは「できる/できない」ではなく、
「やりやすい/やりにくい」という視点を持つと良いです(^^)
- 作業、タスクの種類
- 単純作業;物の組み立て、データ入力 など
- クリエイティブ作業;デザイナー、ライター など
- 人との会話 など
- 環境の条件
- 音の大きさ
- 照明の強さ など
- 対人関係
- 一対一
- 大人数
- 体調、気分の波
- 朝型/夜型
- 緊張しやすいタイミングはあるか
紙・メモアプリなどに書いてみると、
自分の「やりやすい条件」が可視化されます。
その情報は後に、支援機関/医師に相談する際にも、非常に役立ちます。
1つ注意しておきたいのは、
「好きなこと」と「得意なこと」は「必ずしも一致しない」ことです。
「好きだけど」「疲れやすい」活動もあれば、
「特に好きではないけれど」「スムーズにできる」作業もあるでしょう。

(管理人)
「好き/嫌い」を初めから理解するのは、とても難しいです。
しかし、その差を客観的に見ることも、
自己理解の重要な一歩です。
③:「限界を知る」=「自己防衛」
「限界を知る」という言葉には、悪い印象があるかもしれません。
しかし、限界を知ることは「諦めではなく」「自分を守る力」です。
多くの人が体調を崩したり、燃え尽きてしまうのは、
「自分の限界を超えて頑張り続ける」からです。

だからこそ「どのあたりで無理が出るのか」を
前もって把握しておくことが大切です。
- 集中力が切れてしまう
- ➡️ ミスが増える
- 頭痛、めまいがする
- 感情のコントロールが難しくなる
- 「もう少しだけ」と思っても体が動かない
おすすめ;状況をメモしておくと、後から振り返ることもできます

(管理人)
こうしたサインは「絶対に」「無視しないでください」
- 休む
- やり方を変える
- 人に相談する
これらの対応を取ることで、再び立ち上がれる余力を残せます。
限界を知るとは「自分を『壊さないための方法』を身につけること」でもあります。
④:「自分の状態を」「言葉にする」練習をする
自分の状態を誰かに伝えるとき、
うまく言葉にできずに苦労する人は多いです。
福祉サービスを受ける前から、
「どんな状況で」「何が」「どのくらい大変なのか」を整理しておくと、
支援員などに話すときにスムーズになります。
- 【状況】〇〇をしているとき
- 【問題】△△が起こりやすくなる
- 【影響】□□ができなくなる、疲れがたまる
- 【対策】✕✕をすると、少し楽になる
- 【状況】人と話す場面で
- 【問題】緊張しやすい
- 【影響】会話が終わると、強い疲労を感じる
- 【対策】短時間のやりとりなら大丈夫
このように「自分の状態を」「具体的に」「言語化できる」と、
福祉支援の際「自分に合ったサポート」を受けやすくなります。

(管理人)
福祉サービスの利用が始まると、
そのような支援をしてくださるところもあります。
ただし「自己理解をある程度しておく」ことで、
大きなメリットがあります ⬇️
あなた(利用者) ➡️ 「早くから就職活動が出来る」可能性がある
福祉サービス(支援者) ➡️ 「どのような支援が必要か」見えやすい
会社(雇い主/採用・人事担当・上司)⬇️
「どのような配慮があると、働きやすいか」検討しやすい

⑤:「障がい者福祉への理解」を深める
自分の状態を整理したら、次は「障がい者福祉」について調べてみましょう。
ここで大切なのは「支援」=「特別なもの」という「考えを手放す」ことです。

支援とは「今の自分を支える仕組み」であり、
状況に応じて使い分けてよいものです。
- 相談だけでいいかな…
- ➡️ 地域の相談支援センター
- 働く準備がしたい
- ➡️ 就労移行支援
自分の状態を整理しておけば、
「どの支援が自分に合いそうか」も見えやすくなります。
⑥:「見える化」で支援につながる
これまでの「観察」「記録」「整理」を続けていくと、
自分の状態が客観的に見えるようになっていきます。

記録を取ることは、単なるメモではなく「未来の支援への準備」でもあります。
支援を受ける際「客観的な記録」があると、
支援員/医師があなたの状態を理解しやすくなります。
- 一日の中で「疲れやすい時間帯」
- 「集中しやすい環境」の特徴
- 「ストレスを感じる」要因
- 「睡眠」「食事」「体調」の関係
これらの情報は、後に「合理的配慮」「働き方の調整」を
考えるうえで土台になります。

(管理人)
つまり、今の自己理解は、
未来の支援、あなた自身の生きやすさに
直結しているということです。
⑦:「支援を受ける準備」として
自己理解は「自己反省会」では終わりません。
それは「合理的配慮を受けるための準備」でもあります。
「合理的配慮」とは
障がいのある人から「社会的なバリアを取り除いてほしい」
そのような意思が示された場合、
その実施に伴う負担が過重でない範囲で、
バリアを取り除くために必要かつ合理的な対応をすること
https://www.gov-online.go.jp/article/202402/entry-5611.html

自分の状態を「観察/整理し」「言葉にできる」ようになることで、
支援員・医師・家族など、第三者とスムーズに協力できるようになります。
そして支援を受けるときに最も困るのは、
「自分でもよくわからないけど、うまくいかない」という状態です。

(管理人)
もしこの状態で就職したり、福祉サービスを受けても、
「結局何をすれば、自分らしくいられるか」がわかりません。
最終的に「ただ時間を使っているだけ」になってしまいます…
だからこそ、支援を利用する前から
「自分の状態を少しずつ見える化する」ことは、
あなたの生活を守るうえで、とても有効な準備になるのです。
⑧:「できない自分」から「知っている自分」に
自己理解を深めていく途中では、
苦手なこと/限界点が次々と見えてくるかもしれません。

しかし、それを「できない自分」として否定する必要はありません。
むしろ「自分を知っている」ということが「再出発のための最大の力」になります。
特性/限界を理解していれば、無理を避け、
エネルギーを大切に使うことができます。
これは働くときだけでなく、日常生活の中でも役立つスキルです。

今日は調子が悪いな。
家事を減らして、料理だけにしよう

あそこはうるさいな…
行くのは避けよう

体調が落ち着いているときに、まとめて作業しよう…
でも先延ばしの癖があるから、
「〇〇だけ」はやっておこう…
こうした「自己調整の力」は、支援のあり/なしに関係なく、
あなたを守ってくれるでしょう。
おわりに:「自分を知る力」が「生きやすさの土台」になる
「自分の特性・限界を理解すること」は、
支援を受ける前の人にとって、何よりも大切な準備です。
それは「働くためのスキル」ではなく「生きていくための基礎力」と言えます。
- 自分の状態を観察し、記録する
- 得意/不得意を整理する
- 限界を知る/休むタイミングを見極める
- 状況を言葉にして、共有する
- 支援の情報を集め、使い方を知る
こうした積み重ねによって、自分の生活の中に「安心できるリズム」が生まれます。
「福祉を利用する前でも、自分を理解する力は育てられるー」
それは、自分の人生を「自分で選べる」ようになる第一歩でもあります。

(管理人)

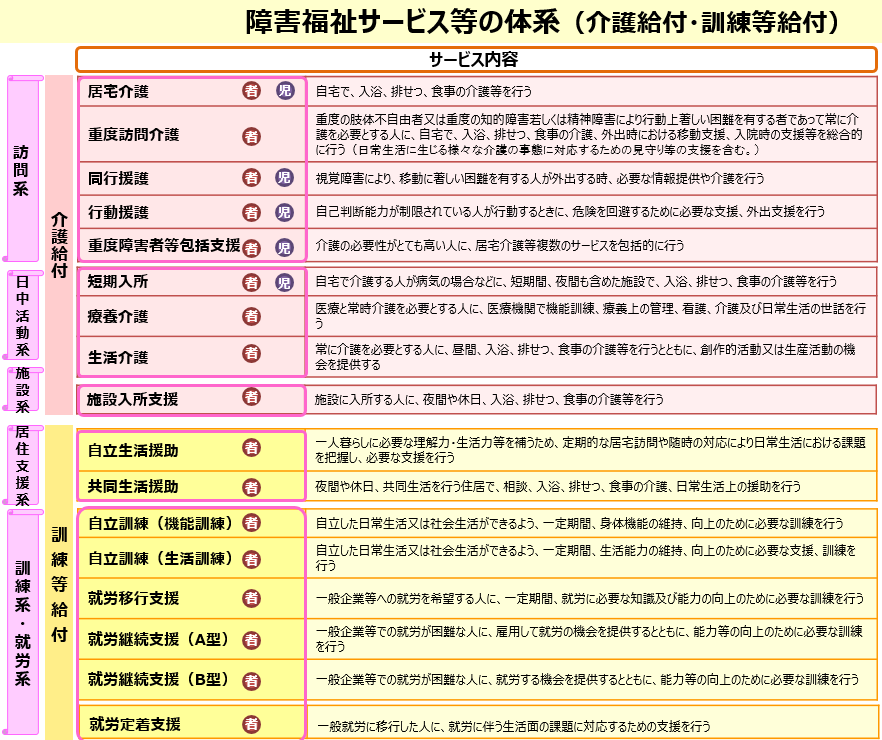


コメント