※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、プロモーションが含まれています

「ASDなそら」管理人のそらです。
ASD(自閉スペクトラム症)当事者の視点で、
仕事・生活に役立つ情報を発信しています(^^)
発達障がい・精神疾患を持つ人が安定して働くためには、
「特性・限界を理解する力」が欠かせません。

(管理人)
この力は単に「自己理解」という言葉で
片づけられるものではありません。
支援者との関わりを通じて、
実践的に磨かれていく力でもあります。
福祉サービスを利用している段階では、
(就労移行支援、就労継続支援など)
支援員・医師・カウンセラー・家族など、
さまざまな人が自分の状況を一緒に見てくれます。
その環境を最大限に活かすために、
以下の3ステップが重要になります。
- 「自分の状態」を「客観的に把握」する
- 「必要に応じて」「周囲に情報を共有」する
- 「限界を自覚」しながら「できる範囲で働く」力を養う
この記事では
「支援を受けながら、自分の特性・限界を理解する」
「働くための基礎を整える」ための考え方を体系的に解説します。
支援のある環境で行う「自己理解」
「自己理解の目的」を整理する
支援機関を利用しているとこう言われることが多いです。

「自己理解」を深めましょうね
ここでいう自己理解とは、
「自分の得意・不得意」「体調の波」
「働く上でのリスク要因を明確にする」ことを指します。
- 「どんな作業なら」集中できるか
- 「どんな環境で」ストレスを感じやすいか
- 体調、気分が「崩れるときの傾向」
- 無理をしやすいタイミング・場面
これらを支援員と一緒に整理することで、
自分に合った働き方の設計図が見えてきます。

(管理人)
これらは「一人で就活している」と
見えてきません。
自己理解を入社前にしなければ、
「最悪の場合」「すぐ休職/退職してしまった」
こうなりかねません…
支援者と共に行う「観察」「記録」
福祉サービスの強みは
「自分以外の視点からのフィードバック」が得られることです。
支援員・スタッフが、日々の行動・作業の様子を見て、
「集中しやすい作業」「負担が大きい時間帯」など、
具体的に指摘してくれることがあります。
- 作業内容、体調の関係
- 対人関係のストレス要因
- 環境調整の効果 など

(管理人)
これらのデータが就職活動・就労定着支援の場面で、
「合理的配慮の根拠」として役に立ちます。
「限界を知る」=「ネガティブではない」
「できないことを明確に」する意味
福祉の支援現場では、しばしば「強みを伸ばす」ことが重視されます。
しかし、限界を知ることも同じくらい重要です。
働く上でのストレス・体調不良 など
➡️「自分の限界を超えた働き方」によって引き起こされるから
限界を知るとは「諦めること」ではなく、
「働き続けられる」「仕事の仕方を見つける」ことを意味します。
まずは支援員と一緒に
「疲れやすい時間帯」「集中が続かない作業」「人間関係の負担」など
限界点を可視化します。
その後「避ける」「調整する」「支援を受ける」方法を検討していきます。

(管理人)
「〇〇したら△△になるから、ダメ」
そんな負の側面に注目すれば、病むこと間違いないです…
「△△にならないためにできること」のように
良い方向で考えていきましょう。
支援機関での「トライ&エラー」を活かす
就労移行支援などでは、実習・軽作業を通じて
自分の適性を試す機会があります。
ここでは「失敗」も重要な情報源です。
- 疲れた
- 集中できなかった
- 思ったより難しかった
支援員はそれらの結果を否定するのではなく、
「どんな条件なら続けられそうか?」と一緒に検討してくれます。
その過程を繰り返していくことが、無理のない働き方の基礎になります。

(管理人)
「失敗を恐れない」ことは勇気のいることです。
しかし、あなた自身の限界を知るためにも、
やって損はありません。
「体調」「感情」の「見える化」
支援を受けながら行う「記録方法」
自分の状態を把握するためには、
主観的な感覚・客観的な記録の両方が必要です。
支援機関では、以下のような記録方法がよく用いられます。
- 日ごとの体調、気分チェックシート
- 作業後の自己評価
- 集中度、疲労度など
- 支援員による客観的な観察メモ
- 医師の診察記録との照合 など
これらの記録を支援者と共有し、月単位で振り返ることで、
自分では気づかなかったパターンを発見できます。

(管理人)
「見える化」は「短期間だと、効果が薄いです」
「長期間」かつ「客観的な視点」で
見ていくのが一番良い方法です。
「数値化」と「言語化」のバランス
体調・感情を数値で表すことは有効ですが、
数字だけでは詳細を捉えきれません。
支援員と共有する際には、
具体的な言葉を添えることで、支援内容がより的確になります。
- 集中はできたが、心が疲れた
- 眠気は少なかったが、頭が重かった

支援を活かした「自己調整」
支援員と作る「行動リスト」
体調が崩れたとき、どう行動すればよいかを事前に決めておくと安心です。
支援員と相談しながら「自分専用」「回復リスト」を作成します。
- 集中できないとき
- ➡️ 短い作業に切り替える
- 不安が強いとき
- ➡️ 支援員に一言伝える
- 例;一人でこの作業ができるか心配なので、
出来るだけ隣りにいていくれませんか?
- 疲れを感じたとき
- ➡️ 10分休憩を取る
このようなリストは、職場実習・一般就労後に
「あなた自身の体調管理」にも応用できます。

(管理人)
ここでも「第三者の視点」が大切です。
支援者との共有で「予防」に転換する
問題が起きてから対応するより、
問題が起こる「一歩手前の状態」を支援者と共有することが大切です。
(就職後は、職場の上司など)
- 前回も同じタイミングで疲れていた
- □□な環境だと、緊張が強い
このような傾向を支援員が把握し、当事者と一緒に対策を立てることで、
問題を軽くすることが可能になります。
これにより「問題解決型の支援」から
「予防型の支援」へと移行しやすくなります。

(管理人)
そのため福祉サービスを利用している方は
「トライ&エラー」を繰り返すことが大切なのです。
支援の中で育つ「自己開示」「援助要請」
「援助要請」=「自己管理」の一部
支援機関では「SOSを出す練習」も重要な支援項目です。
援助要請は単なる「助けを求める行為」ではなく、
自分の状態を把握し、適切な相手に「情報を伝えるスキル」です。
- 「どんなとき」に助けが必要になるのか
- 「誰に」「どんな言葉で」伝えるとスムーズか
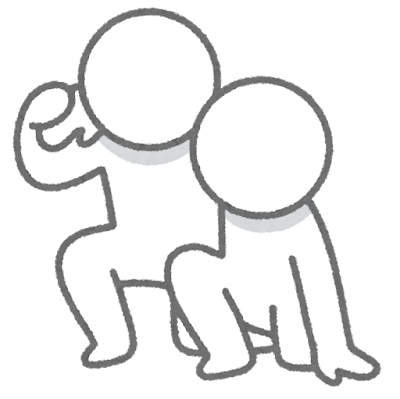
「共有の範囲」を考える
支援の現場では「情報を誰と共有するか」も重要です。
- 福祉サービスの職員さん
- 主治医
- 家族
- 職場の人事担当者
- 上司、同僚 など
- 上司、同僚 など
それぞれに伝える内容・深さを調整することで、
プライバシーを守りながら適切なサポートを受けられます。
この「共有の線引き」を支援員と一緒に検討しておくと、
就職後も安心して援助を受けることができます。

(管理人)
たとえば…
「情報Aは、職場の同じ部署・就労移行の職員さんに」
「情報Bは、主治医だけに」
できる限り「自分一人で抱え込まないようにしましょう」
就職につなげる「自己理解の応用」
「合理的配慮の根拠」として使う
支援を通じて得た記録・分析結果は、就活の際、
合理的配慮の要望を伝える根拠になります。
具体的な情報を整理しておくことで、企業側にも理解されやすくなります。
- 「静かな作業環境では、集中でき、能力を十分発揮できる」
- 「急な予定変更に弱く、パニックになることがある」
- 「休憩をこまめにとると、体調が安定する」

(管理人)
上記の内容が「履歴書」「職務経歴書」「面接」以外でも
役に立つ場面があります。
「主治医との会話」が最たる例です。
支援終了後も続ける「自己観察」
支援機関を卒業したあとも、
自分の状態を観察し続けることが大切です。
支援中に学んだ記録方法・調整スキルは、
そのまま職場で「自己管理」に活かせます。
支援者の助けがなくなっても、
培った「自分を見る力」が支えになります。

(管理人)
就職後に方法を変えたり、
やめてしまってもOKです。
その時は「就労定着支援」など、
福祉サービスを利用して、
第三者視点を確保できるとより良いですね。
あなた自身を見る力が身についてきた、
何よりの証拠です(*^^*)
おわりに:「支援を通じて」「自分を知る」「支える力」を育てよう
支援機関を利用する期間は、単に職業訓練を受ける時間ではなく、
自分を理解し、他者と協力して働くための基礎を作る時間です。
ここで培った「自分の特性と限界を理解する力」は、
就職後の安定にも直結します。
- 自分の状態を観察する
- 支援者と共有しながら、情報を整理する
- 必要な支援を自ら選び取る
この「働きやすさの土台」を作り、
いろいろな経験を積み重ねた先には、
福祉の力を借りなくても「働き続けることができる」ようになるでしょう。

(管理人)



コメント