※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、プロモーションが含まれています

「ASDなそら」管理人のそらです。
ASD(自閉スペクトラム症)当事者の視点で、
仕事・生活に役立つ情報を発信しています(^^)
職場における「働きやすさ」は、
単に「作業効率」「スキル」だけで決まるものではありません。
物理的・心理的・社会的な「環境の影響」が大きく、
「少しの工夫」で、働きやすさが大きく変わります
ここでいう「環境」とは、主に以下の3つの要素を指します。
- 物理的環境
- 作業場所
- 作業手順の構造
- 作業道具の配置 など
- 人間関係・コミュニケーション環境
- 上司、同僚との関係
- 報連相のルール【報告・連絡・相談】 など
- 自己管理環境
- 「体調」「生活リズム」「感情」「思考の管理」 など
これらの環境を整えることは、
職場で無理なく力を発揮するための基盤となります。
この記事では、ASD当事者が「特に意識すべき」
「職場環境の整え方」を詳しく解説します。
「許可が苦手」をやわらげる
「許可を取る」場面の整理
職場では多くの場面で「許可を取る」必要があります。
これを苦手と感じる人は少なくありません。
- 相手の領域に踏み込む不安
- 相手の反応を予測できない
- 不安が先行する
- 衝突の可能性
- 自分の意見が拒否されたとき、心理的負荷が大きい
- 手続きの面倒さ
- 許可申請の手順 ➡️ 複雑、煩雑
- 独立性の欲求
- 「頻繁に許可を求めること」=「自分の自由を制限している」

「許可を取りやすくする」工夫
許可を取るストレスを軽減するためには、
「手順の可視化」「段階的な実践」が有効です。
- 質問内容を整理する
- 事前にメモ、チャットで伝える内容をまとめる
- タイミングを確認する
- 『今、お時間よろしいですか?』と前置きする
- 相談の形を取る
- 『こういう考えがありますが、どう思われますか?』と聞く
- 自己判断の範囲を確認する
- 「この件は今後、自己判断で進めてよいか」を事前に明確化

(管理人)
これらを意識することで「許可を取る行為」を
「心理的負担の少ない作業」に変えることができます。
「伺い(うかがい)を立てる」言い方を覚えると、
最初は違和感を感じるかもしれません…
ただし「上司がいる」以上、
身につけておいて損はありません。
「職業準備性ピラミッド」を基準にする
厚生労働省が公開している「職業準備性ピラミッド」は、
働く力を整理するうえで非常に有用です。
- 健康管理
- 「体調」「障がい理解」「服薬管理」 など
- 日常生活管理
- 「生活リズム」「金銭管理」「食事」 など
- 対人スキル
- 「挨拶」「協調性」「報連相」 など
- 基本的労働習慣
- 「出勤」「ルール遵守」「スケジュール管理」
- 職業適性
- 「スキル」「専門性」「適職判断」
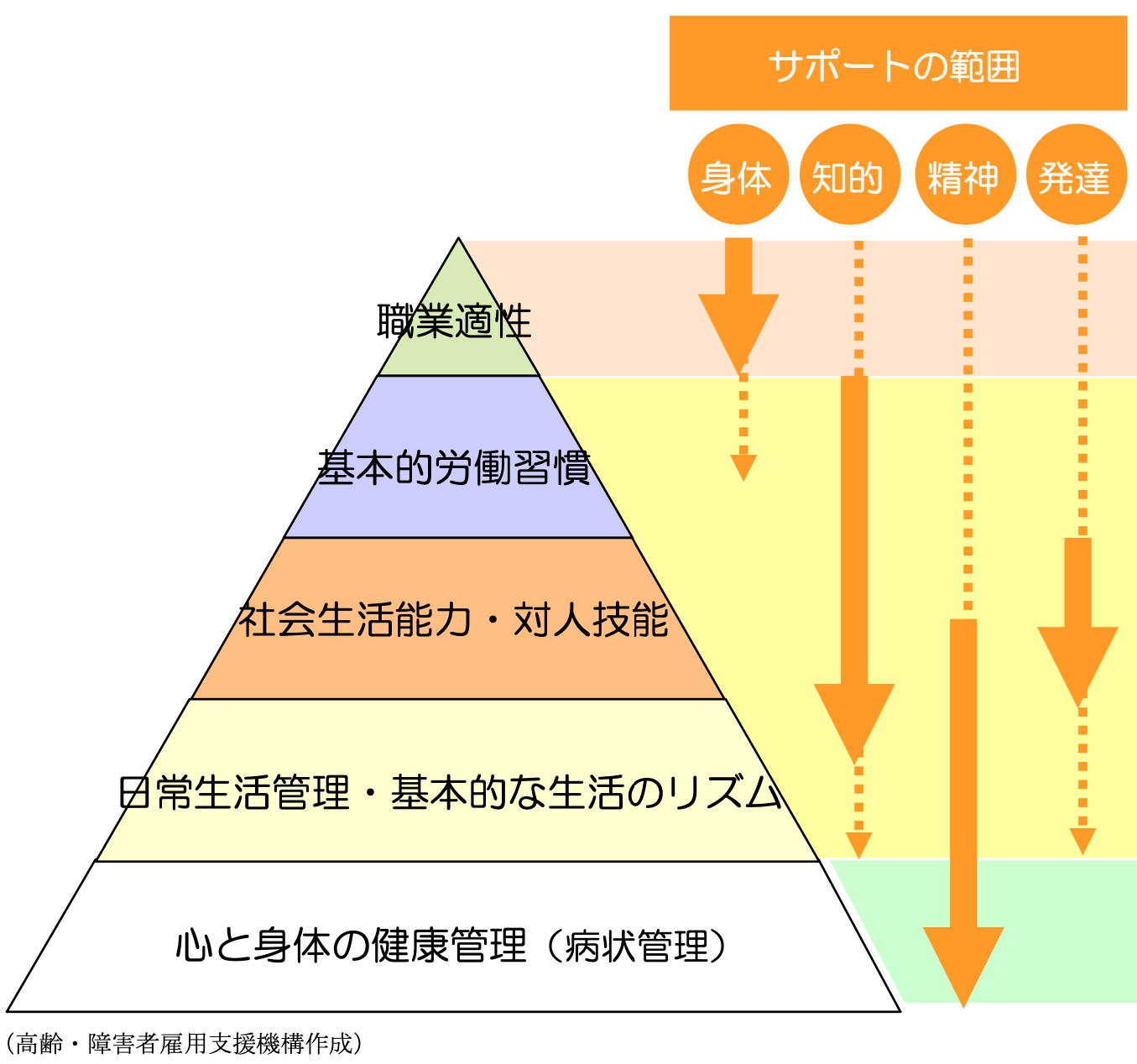
ピラミッドの下から順に身につけることで、
職場で安定して働く力が形成されます。
「健康管理」体調・心の状態を可視化
健康管理はピラミッドの最下層であり、
働く上での土台です。
- 睡眠、食事、運動
- 一定のリズムで生活する
- 服薬管理
- 服薬の有無、タイミングを自己管理
- 体調変化の把握
- 疲労、ストレスの兆候を自覚する
- 休養、調整を行う
- 障がい特性の理解
- 自分の反応、疲労傾向を把握する
- 職場で説明できる状態にする
健康管理を可視化することで、
「作業能力」「集中力の安定」につながります。

(管理人)
「健康第一」と言われるように、
身体・心の調子が良くなければ、
「本当に」何もできません…
「日常生活管理」生活の自立度を上げる
日常生活管理とは、日々の生活を計画的に回せる能力を指します。
- 生活リズムの安定
- 朝起きる、夜寝るの時間を一定に保つ
- 食事の管理
- 朝食を抜かない
- 栄養バランスを意識
- 家計管理
- 収入、支出を把握する
- 計画的に使う
- 生活の段取り化
- 無理のない段取りを作る
- 前日の夜に朝の準備を済ませる など
- 無理のない段取りを作る
生活管理は単なる「生活リズムを作る」ことではなく、
職場で安定して働くための基礎です。

「対人スキル」人との信頼関係を築く
対人スキルは、
職場での円滑なコミュニケーション・チームワークの基盤です。
- 挨拶、礼儀
- 朝の挨拶
- 帰宅時の報告
- 場面に合った言葉遣い
- 口調、表現を調整する
- 相手に誤解を与えない
- 報連相
- 「報告」「連絡」「相談」をタイムリーに行う
- 感情コントロール
- 急な変更、指摘に冷静に対応する
対人スキルは、習得に時間がかかるものの、
ピラミッドの土台が整うことで自然と力が伸びます。
「職場環境」を「物理的に」整える
物理的環境は、作業効率・集中力に大きく影響します。
- 作業スペースの整理
- 必要なものだけを配置する
- 不要な刺激を減らす
- 作業手順の可視化
- 図解、チェックリストを活用する
- 迷わず作業できるようにする
- 作業道具の固定配置
- 頻繁に使う道具 ➡️ 定位置に置く
これにより、無駄なストレスを減らし、
集中できる状態を維持できます。

(管理人)
「自宅の部屋を掃除すること」と同じなのです。
「コミュニケーション」環境の整備
職場での心理的負荷を減らすためには、
コミュニケーション環境の整備が重要です。
- 報連相ルールの明確化
- 「どの」タイミングで「誰に」「何を」報告するか
- 事前に整理する
- 「許可」「相談」のタイミングを決める
- 一日の特定の時間帯を相談時間に設定する
- フィードバックを受けやすくする
- 指摘、アドバイスを受け入れやすい形式を活用する
- 書面、チャット など
- 指摘、アドバイスを受け入れやすい形式を活用する
コミュニケーション環境を整えることで、心理的負荷が軽減され、
作業に集中できるようになります。

(管理人)
「心理的安全性」を「自分から」確保していきましょう。
こうすることで、
他人と「安心できる」コミュニケーション環境を
作ることができます。
「自己管理環境」の構築
自己管理環境は、体調・感情・思考の自己調整能力を高めることを指します。
- 「体調」「感情」の記録
- 日々の疲労、ストレスを記録する
- 変化に対応する
- ルーティンの固定
- 朝、昼、夜の行動パターンを習慣化
- 休憩と回復の計画
- 作業の合間に休憩を挟む
- 集中力を維持
これらの工夫により、自分の限界を理解し、
無理のない働き方を維持できます。

(管理人)
「自分ひとりじゃ、到底できないよ…」
そんな方は、主治医・専門家など
第三者と意見を交わしながら行うとよいです(^^)
「小さな工夫の積み重ね」が働きやすさを作る
環境を整えることは、一度に完璧に行う必要はありません。
大切なのは「小さな工夫の積み重ね」です。
- メモ、チェックリストで作業手順を可視化
- 朝、夜のルーティンを固定
- 報連相のタイミングを事前に決める
- 作業スペースを整理して刺激を減らす
- 許可、相談の手順を簡素化する
少しずつ改善していくことで、
職場での負担が減り、働きやすさが増します。

(管理人)
それぞれは「小さな一歩」です。
しかし「1つ1つ積み重ねていく」ことが、
今後生きていく上で大切になってきます。
おわりに:環境を整え、自分に合った働き方を実現しよう
ASD当事者が職場で力を発揮するためには、
以下の「3つの環境」+「職業準備性ピラミッド」を
意識することが重要です。
- 「物理的」環境
- 作業スペース
- 手順
- 道具の配置
- 「コミュニケーション」環境
- 報連相ルール
- 「相談」「許可」の手順
- 「自己管理」環境
- 「体調」「感情」「生活リズム」「思考」の管理
+ 職業準備性ピラミッドの土台である
- 「健康管理」
- 「日常生活管理」
- 「対人スキル」
これらを整えることで、
安定して働く力が形成されます
環境を整えることは、単なる効率化ではなく、
働く上での心理的・物理的負荷を減らすための基本です。

(管理人)
「小さな工夫の積み重ね」が、
あなたの働きやすさを作る「第一歩」です(*^^*)
焦らず、少しずつ環境を整え、自分に合った働き方を作りましょう。

(管理人)
質問などあれば、お気軽にコメントしてくださいね。
Xでもお待ちしております(^^)



コメント