※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、プロモーションが含まれています

「ASDなそら」管理人のそらです。
ASD(自閉スペクトラム症)当事者の視点で、
仕事・生活に役立つ情報を発信しています(^^)
人間は、できないことや苦手なことに目が向きがちですが、
本当に大切なのは「できること”」に気づき「それを活かす」ことです。
ASDの特性は、働きづらい原因になりますが、
同時に独自の強みにもなります。
自分の特性と長所を理解し、それを活かす働き方を見つけることが、
充実した人生への鍵となります。
今回はその具体的方法を紹介していきます。
コツコツ実践していけば、必ず道は開けますよ。
① 自分の特性・長所を知る
ASDの特性は一人ひとり異なりますが、傾向として共通する特徴があります。
それを「困難」と捉えるのではなく、
「使い方次第で強みにもなる資質」として理解していくことが大切です。

まずは、自分自身がどんな特性を持っているのか、
どんな場面で能力を発揮しやすいのかに気づくことから始めましょう。
共通するASDの特性・傾向
- 「疲労が溜まりやすい」
- ↔️ 一つの課題に「深く集中できる」
- 「興味のないこと」には集中できない
- ↔️ 「細かい部分」に気づきやすい
- 「予測不能な変化」が苦手
- ↔️ 「安定した環境」を好む
これらの特性は、裏を返せば職場での武器になります。
- 集中力 ➡️ 他の人が嫌がる細かい作業を、ミスなくやり切る力
- 変化が苦手 ➡️ 一貫性・正確性がある

(管理人)
逆に、
- 疲労が溜まりやすい
- 臨機応変な対応は苦手 など
デメリットの部分は配慮をしてもらうと、
環境改善につながります。
自分の特性・長所を把握する方法
特性だけでなく、長所=自分の「強み」を把握することも非常に重要です。
特性は自分の取扱説明書のようなものであり、
長所はそれを活かすエンジンのようなものです。
- 自己分析ツールを使う
- 自分の資質・価値観を明確にする

(管理人)
新品の購入をおすすめします。
本についてくるコードで、検査を受けていただき、
その後本を読んでいただくと
自身の理解度がより深まります。
- 過去の成功体験を振り返る
- 「何が良かったか」「どんな工夫をしたか」「誰に褒められたか」などを掘り下げる
- 自分の得意なこと・自然にできることに注目する
- 例:「メモを取るのが早い」「道順を覚えるのが得意」など
- 周囲の人に「自分の良いところ・強み」を聞いてみる
- 自分では気づいていない、意外な長所を見つけられる
- 小さな挑戦を繰り返す
- 自分がどんな場面で「力を発揮しやすいか」を観察する
- 周囲の人に見てもらうと、さらに◎

(管理人)
障がい者にとって、自分のやりやすさ・心地よさは、
働く上で非常に大切な指針です。
加えて特性・長所を両方認識することで、
職場・働き方の選択がより具体的&前向きなものになります。
入社前に、できる限り人間関係・環境面が
整っていることが理想です。(次に紹介します)
② 適切な職場環境を作る
自分の特性が分かってきたら、
次はそれを活かす環境を整えることが必要です。
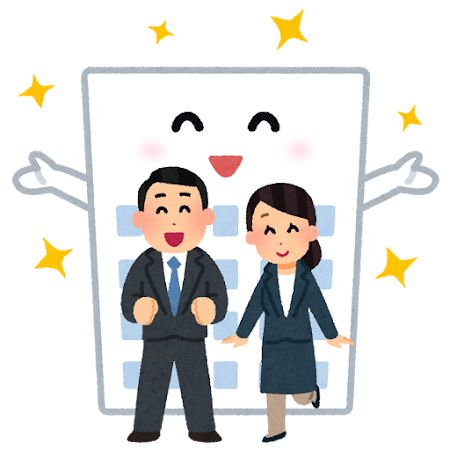
環境に働き方を合わせるのではなく、
自分に合った環境を選び取る・作っていくという視点を持つことがポイントです。
快適な作業空間の条件
ASDの方にとって、物理的な環境の影響は非常に大きいです。
感覚過敏がある場合、音・光・視覚刺激などで集中が妨げられることもあります。
- 騒音・視覚刺激が少ない場所を選ぶ
- パーテーション・仕切りを設置する
- 人の気配が気にならないようにする
- イヤーマフ・耳栓で調整する
- エアコン・コピー機など、機械音が気になる場合

(管理人)
私自身も、以下の対策をしています。
- 座席を外向きにする
- 他人が視界に入らないようにする
- ヘッドホンを着用する
- 機械音がうるさく、集中できない
いずれにせよ第一に、上司への相談です。
明確な指示と伝え方
曖昧な表現、非言語のニュアンスだけに頼る指示は、
特にASD当事者は誤解を生みやすいです。
そのため「明確で視覚的に伝える工夫」が大切です。

- 具体的な名称で伝えてもらうようにする
- 「これ」「あれ」「それ」「どれ」のこそあど言葉を避ける
- 方向を指差し・図で補ってもらう
- マニュアル・手順書を、文字・図付きで準備してもらう
- 自分で作るのも○

(管理人)
すべて実践して、
特に「具体的名称を使う」が大切と分かりました。
「こそあど言葉」は。呪文にしか聞こえません…
スケジュールの工夫
予定変更・急な指示に混乱しやすい特性を踏まえ、
予測可能なスケジュール・柔軟な対応策が重要になります。
- 先の見通しを「見える化」しておく
- 例:Googleカレンダー、紙の予定表に書く
- 予定の変更があるとき ➡️ 事前に伝えてもらうよう依頼する
- 一度覚えた業務や手順は極力変えない
- 慣れた流れで働けるようする

(管理人)
「スケジュールの見える化」は極めて重要です。
柔軟な勤務制度
現代は多様な働き方が選べる時代です。
あなたのライフスタイルや特性に合った働き方を選ぶことが、
継続的な就労に直結します。
- テレワーク
- 自宅から安心して業務に取り組む
- 短時間から始めて、徐々に慣れていく
- 週2〜3回 ➡️ 平日出勤
- 勤務時間・業務内容を調整していく
- 月に1回など、定期的に上司との面談の機会を設ける
- 外部の「ジョブコーチ」をサポートに入れる
- 安心して働ける環境を作りやすくなる
- 企業在籍型もあります
- 安心して働ける環境を作りやすくなる

(管理人)
勤務時間・業務内容の調整は、
あなたの可能性の拡大のために、避けては通れません。
「ジョブコーチ」を利用すると、
上司の意見に加えて、
第三者からのフィードバックをもらうことが可能なので、
おすすめです。
③ 効果的なタスク管理
ASDの特性を持つ人は、
いくつもの作業を並行するマルチタスクが苦手だったり、
突然の優先順位変更に戸惑いやすかったりします。

そこで、タスクを「見える化」して「順番に処理する」方法が非常に有効です。
タスク管理のポイント
- タスクを一覧にする
- Google ToDoリスト、紙のメモなどを利用する
- その日の優先度が高いものを3つに絞り、1つずつ確実にこなしていく
- 上司と「今日中にやるべきこと」を確認しておく
- 出勤直後にすると◎

(管理人)
「やることリスト」はプライベートでも有効です。
- 定期通院
- 障がい者手帳の更新
- 自立支援医療の更新 など
特に役所に出向き、
「更新」する作業は忘れがちです。
対策として「更新直後に予定に入れてしまう」のが
最も有効です。
時間管理の工夫
集中力をコントロールしながら効率よく作業するには、
「時間の枠を区切る」ことが効果的です。
- 作業時間と休憩時間を1セットとし、最初に決めてしまう
- 例:30分の作業+1分程度の小休止
- お昼休みなど、長い休憩時間を有効活用する
- 時間を視覚的に確認できるようにする
- スマホのアプリ、タイマーなど

(管理人)
「30分の作業+1分程度の小休止」に慣れてくると
「1時間の作業+2〜3分の小休止」になります。
より作業時間を伸ばすことも可能ですが、
無理しない程度に調整していく必要があります。
視覚的な工夫
- タスクを色分けして一覧にする
- 例:赤=優先度高、青=習慣業務 など
- 完了したタスクにチェックを入れることで、達成感を得る
- 2重線で消してしまうのも○
- 「やったことリスト」を毎日残し、自信につなげる

(管理人)
タスクの色分けをすることで、
スケジュールをさっと見ても
「今日は忙しいかも…」と察することが可能です。
「完了したタスク」が貯まってくると、
『これだけのことをやったのか…』と
成長を可視化できるのは大きいです(^^)
④ コミュニケーションの工夫
職場での人間関係は、
ASD当事者にとって非常に大きなストレス源となることもあります。
特に、暗黙の了解や「察する」文化が強い場では、混乱が生じやすくなります。

(管理人)
「暗黙のルール」はASDにとって、最も大きなハードルです。
これを乗り越えられると、働きやすさが格段に上がります。
そのため、コミュニケーションをできるだけ明確・可視化する工夫が欠かせません。
意識すべき表現の工夫
- 具体的な言葉を選ぶようにする
- 自分からも「曖昧な言い方」を避ける
- 指示を受けた際には「〜という意味でよろしいですか?」と復唱して確認する
- すれ違いが起きたときは、責めない
- 事実ベースで整理する習慣を持つ

(管理人)
ここで大事なのが
「自分からも抽象的な言葉回しを避ける」ことです。
例:『これ』は『どこに』直せばよいですか?
自分が使ってしまうと、
相手も使っても大丈夫なのかな、
そう思ってしまうためです。
修正例:ガムテープは、備品棚に直せばよいですか?
例のように、治せると良いです(^^)
物の名前がわからない場合のみに
「「これ」「あれ」「それ」「どれ」のこそあど言葉」を使えばOKです
書き言葉の活用
- メール、チャットでのやりとりを提案する
- 会話に不安がある場合
- まずメモを書いてから発言する
- 思考や感情が整理できていないときほど◎
- モバイル端末、メモ・ペンを常備する
- すぐに記録が取れるようにする

(管理人)
「メモ・ペン」はいかなる場合でも、必需品です。
持っておくだけで、会話に対する安心感が違います
感情的になったときの対処
- 一度その場を離れて深呼吸する
- 相手に「少し時間をください」と伝えて距離を取る
- 気持ちが落ち着いてから、整理した言葉で話す

(管理人)
支援者からみて
普段の様子と違う場合、これらの対処法は有効です。
- 疲労が溜まっているとき
- パニックになったとき など
⑤ 自己成長と長期目標
働き続けるためには、スキルアップや自信の積み重ねも重要です。
しかし、急に大きな目標を設定しても長続きしません。
まずは「今日できたこと」に目を向けることからスタートしましょう。
日常でできる習慣
- 朝起きる時間を固定する(寝る時間もすると◎)
- 生活リズムを整える
- 一日一つだけ「やるべきこと」を決めて達成する
- 小さな成功体験を記録し、自己肯定感を高める

(管理人)
これら1つ1つは小さな一歩ですが、
「働きたい」気持ちをさらに高めるためには、
もってこいの方法です。
フィードバックの受け止め方
- 指摘は「自分を否定された」と思わない
- 「伸びるチャンス」と捉える➡️これ大事
- 改善点を具体的にメモに書き出し、行動に落とし込む
- 行動の過程も大事
- 感情的になったら一呼吸おいて、自分の価値を再確認する

(管理人)
指摘や叱られたときは「自分ってダメだ…」
そう思いがちです。
「自身で思考を変えることが難しい時期」は
「上司などの第3者が優しく接する」のが重要です。
得意を伸ばす意識
- 「苦手を直す」よりも「得意を伸ばす」方が成長につながりやすい
- 好きなこと・得意なことが重なる分野に集中する
- 苦手な業務は他人に依頼したり、ツールに頼って対応する

(管理人)
苦手なことに目が行きがちですが、
「得意なことを伸ばす」のが極めて有効です。
苦手なことは遠慮なく、他人や便利なツールを頼りましょう。
私も、そうしています(まだまだ頼ることには慣れていませんが…)
定期的な振り返り
- 自分の調子、仕事の出来を振り返る
- 1週間に1回が○
- 「できたことリスト」「改善したいことリスト」を書く
- 月に1度でOK
- 環境や業務が合っているかどうか、定期的に見直す
- 3ヶ月に1回のペース

(管理人)
一度上司と相談して始めたことは、できる限り続けましょう。
そして、定期的な面談などで振り返りをし、
あなたの働く環境を整えていきましょう。
だんだんと「働く」ことへの恐怖心が減ってくることと思います
最後に
ASDの特性はときに「障害」として働きにくさを生むことがありますが、
適切な工夫と環境調整によって「強み」に変えることが可能です。
- 完璧を目指さない
- 自分のペースで進む
- 他人と比べない
- 昨日の自分と比べる
- 長所を活かす
- 自信と安心感を育てる
あなたにしかない価値があります。その価値を活かせる職場や働き方は、必ず見つかります。
少しずつ、自分らしい未来を築いていきましょう。
あなたはひとりではありません。

(管理人)
質問などあれば、お気軽にコメントしてくださいね。
Xでもお待ちしております(^^)




コメント