※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、プロモーションが含まれています

「ASDなそら」管理人のそらです。
ASD(自閉スペクトラム症)当事者の視点で、
仕事・生活に役立つ情報を発信しています(^^)
今回は小学校卒業までを記します。
楽しかった唯一の習い事
低学年(1,2年生)の頃に両親から
「英会話に通ってみない?」と言われ、言われるまま行くことになります。
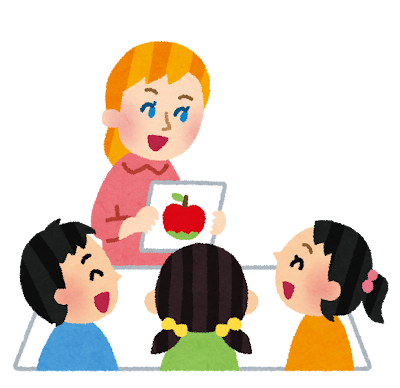
これがとてつもなく楽しかったのです。
- 新しい言語
- 新しい人間関係
- 新しい環境 など
触れるものすべてが新鮮で、
外国人との触れ合いもありずっと楽しい記憶しかありません。
英会話の日になると、ウキウキだった気がします。
- 新しい単語を覚えるのは、楽しい
- 授業ばかりでなく、ゲームもやるので、楽しい
- 聞ける・話せる・書ける・読めるようになる
幼少期に母国語以外の言語を習得するのは、極めて大きいことです。
しかし英語は当時、小学校の教育方針には含まれていませんでした。
まだ外国語活動がなかった時期だったのです。
そのため学校内で役に立った事はありませんでした。
ゲームが友達になる
自分が幼稚園の時は「一人遊び」が自分の中の主流でした。
それが加速するものを、6年生の時に「自分の力で」手に入れました。
「ニンテンドーDS Lite」です。
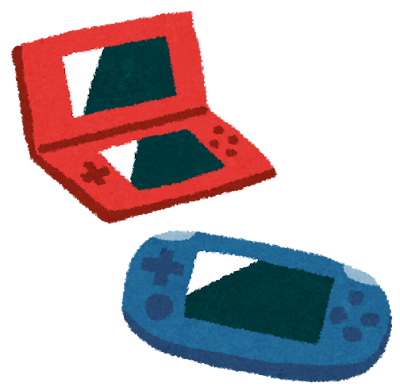
家族内ではゲームは買ってもらえませんでした。
父方の実家にはファミコンの箱があったりと、
過去にゲームしていたのかなと、その時思いました。
その後父から聞いたのですが、かなりの「オタク」だったらそうです。
ただ父が一人暮らしを始め、実家を離れた際に
多くが捨てられたそうです…

そして学校での話題はゲームばかり。
周りの話についていくことが全くできませんでした。
共通の話題がないからこそ一人遊びが中心だった、と考えています。

そのため、お年玉に加えて手元のお金で、本体とソフトを一緒に購入しました。
「ポケットモンスターダイヤモンド」が人生で一番最初のゲームでした。
かなりやり込んだ記憶があります。
ポケモンのおかげで、少しずつゲームの話題が理解できるようになります。
友達ともゲームをする機会が少しずつ増えていきました。
主に、友達の家のプレイステーションで桃太郎電鉄を一緒に遊んでいました。
本を読むのは好きだけど…
更に一人遊びは加速します。
「読書」です。
幼稚園の頃の記憶が蘇ります。
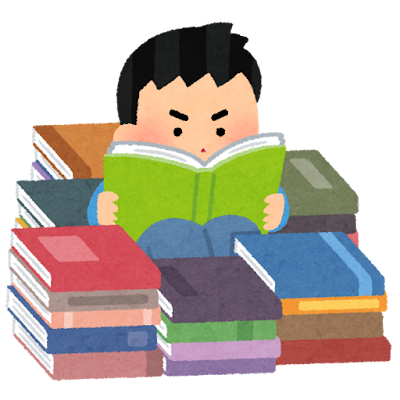
小学校のクラブ活動で読書クラブを選んで、
小学校の図書館に多く通い、様々なジャンルの書籍を読んでいました。
しかし小学生の頃、小説を読むことは少なかったと思います。
物語を想像することが容易で、現実まで引きずってしまうためです。
この事は幼稚園の頃から分かっていた「想像力が強い」に繋がっています。
読書好き、といえば国語はどうだったのかというと
『面白くないなぁ…』と思っていました。
実際、国語のテストもそれほど点数は高くありませんでした。
- 作者はどう考えているのか
- 主人公は何を思っているのか…
そういう事がわかりませんでした。
加えて読書感想文を書く事も苦手でした。
あらすじを書かずに、感想だけで原稿用紙◯枚書くー
好きでもない物語を読んで感想を書くことは何よりも辛いことでした。
この頃から、公共の図書館にも通うことが多くなります。
- とにかく広い
- 書籍は、比べ物にならないほど多い
- 種類も豊富
最初は、図鑑を多く借りて読んでいました。
特に小学生の頃は、日本全国の駅図鑑をいつも借りて、
貪るように読んでいました。
『暗記ってする意味あるの?』
一番辛かったことは「文章が覚えられない!」です。
「文章を暗記して、それを全部言えたらOK」というものです。
6年生の時、担任の先生が総合的な学習の時間の中で行っていました。
文章もそれなりの長さがありました。

周りの人は覚えられてる。
しかし自分は覚えられない。
『こんなの覚えられないよ…』 教室で泣いた記憶があります。
『覚えて何になるの…?』と泣きながら考えていました。

結局どうにか頑張って覚えて、全文言えることができたのですが、
『暗記って意味あるのかな…?』と考えていました。
「図画工作」が一番嫌いな科目
文章が覚えられないことに加えて辛かったのが図工の時間です。
幼稚園の頃「絵を描く」のが苦手だった自分はただただ辛かったです。
特に自分オリジナルの作品を作る事が苦手でした。
紙粘土で踊っているポーズを作っていたら、
全く違うものができてしまい、別の題名をつけざるを得なかった…
そんなエピソードがあります。
さらに苦手だったのが夏休みにある「読書感想画」です。
本を読んで、感想を書く事も苦行でした。
(この記事内「本を読むのは好きだけど…」参照)
図工が苦手な自分に、追い打ちをかけたのが感想画でした。
- 「下書き」をどうするか
- 「どの色」の絵の具を使うか
- 「いつ」やるか
どんどん後回しになり、
夏休みの最後に母親にガヤガヤ言われて、追い込んでやった記憶があります。
本当に嫌でしたね…
「カードゲーム、面白そう」
小学生の頃は、子供会に入会してました。
今はすでにないものかもしれません。
近所の小学生を集めて、保護者がイベントを企画していました。
自分はその集まりには興味がなく、「時間の無駄」を感じていました。
強制的だったためとても苦痛でした。
3or4年生の時、とあるイベント中の出来事。
上級生が「遊戯王」で遊んでいました。

「へぇ~面白そう」自分は興味を持ちます。
クリスマスプレゼントに頼んでもらうところまでは良かったのですが、
当時の自分にはルールが複雑、かつ難しくて理解ができませんでした。
その後高学年になると、
桃鉄を遊んでいる友達とプレイするようになります。
複雑なルールがなんとなく理解できるようになり、楽しかった記憶があります。
「けん玉」で褒められる
小学生の頃、学校ではけん玉が流行していました。
総合的な活動の時間で、学年の枠を超えてやっていた記憶があります。
当然、自分もその熱狂の中にいました。
難しい技ができれば出来るほど面白いのです。
自宅でもしばしば練習していたら、
偶然来ていた祖父に「今度親戚の前で見せてよ」と言われたので
実際にやって見せることとなりました。
そしたら技は決まる、大絶賛される、でこれでもかと褒められました。
自分が主役で写真まで撮られました。
(今でも祖父母宅に飾ってあります)
数少ない、家族での良い記憶の1つです。

運動が楽しく感じる
6年間通じて、なわとびを体育の時間にやっていました。
しかし運動は苦手でした。体型もふっくらしていました。
逆上がりはできず、持久走も下から数えたほうが早いほどでした。
ただし、それが変わる出来事があります。
2重跳びが出来るようになったのです。

さらに「はやぶさ」という技ができるようになりました。
「はやぶさ」とは
「2重跳び」+「あや跳び」のこと。
どうしてできるようになったかは、覚えていません。
それを体育の時間にやった時、学年全員から見られていた気がします。
「はやぶさなんて出来る人、いるの?」
それくらいレアな存在だったのです。嬉しかった記憶があります。



コメント