※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、プロモーションが含まれています

「ASDなそら」管理人のそらです。
ASD(自閉スペクトラム症)当事者の視点で、
仕事・生活に役立つ情報を発信しています(^^)
発達障がい(ASDなど)の特性を持つ人にとって、
「生きづらさ」や「うまくいかないこと」は日常の中にたくさんあります。

(管理人)
けれども、環境を少し工夫したり、
自分に合ったやり方を知ったりすることで、
「できない」と思っていたことが「できる」ようになることもあります。
自分も「一手間かける」ことで
困難を乗り越えたことが多くありました。
この記事では、最新技術に依存しすぎず、
ASD当事者が長く活用できる「自分を自分で管理する方法」と
「いつでも役に立つ支援・工夫」をまとめて紹介します。
焦らず、自分に合ったやり方を見つけていく参考になれば幸いです。
タスク・予定管理:頭の中から『外に出す』
ASD特性の一つに「ワーキングメモリの弱さ」があります。
頭の中だけでスケジュールやタスクを記憶しようとすると、
混乱や抜け漏れが起きやすくなります。

(管理人)
実際に私も、忘れていたことが「多くあります」
『これくらいなら、覚えていられるかな』
そう思っても、
仕事が終わる頃もしくは翌日、
忘れていることに気がついてしまうんですよね…
- 「予定の見える化」をする
- Googleカレンダー、紙のカレンダー など
- 「やるべきこと」をリストアップ
- 「やったことリスト」を作成する
- 達成感を可視化できる

(管理人)
「Googleカレンダー」なら
上記3つ、すべてこなすことが可能です。
私も導入後「予定の見える化」で
過度な疲れを感じなくなりました

(管理人)
『全部覚えておこう』は
『結局、全部忘れてしまいます』
『見える化』で脳の負担を減らすことが自己管理の基礎です。
感情・体調ログを取る:自分の波を知る
感情や体調の波を「パターン」として把握できると、
事前に対処できたり、無理を避ける判断がしやすくなります。

(管理人)
私の場合…
- 頭痛+αの症状が来る
➡️ 限界のサイン
➡️ 美味しいものでも食べる - ゆううつな気分
➡️ 外出して気分転換
「頭の外に出す」ことで
よりパターンがはっきり見えてきます。
- 1日1回の気分・体調を記録
- 紙の日記、スマホのメモ など
- 疲労や集中力を数字にして、可視化する
- 「0~10」で表す
- 「疲れの原因」「落ち込みやすい日」を発見する
- 週・月単位で振り返ってみる

(管理人)
私は1日のおわりに、
スマホのメモアプリを開いて、
今日の良かったこと・体調を振り返ります。
- 今日も出勤できた
- 一日お仕事できた
- ただ、めちゃくちゃ疲れた…
小さな幸せを見つけながら、日々、
私自身の「体調・気分の波」を
俯瞰しています。

(管理人)
「完全・カンペキな記録」を目指すのではなく、
「ざっくり」「続けること」が大切です。
習慣を作る:「自動化」すればラクになる
毎日の「何をするか決める」という判断自体が
ASD当事者にとっては負担になりがちです。
「習慣(ルーティン)にする」ことで脳の負荷が下がります。

(管理人)
私も、普段と違うことをすると強い疲れを感じます。
そういう日に限って、翌日お仕事だったりしますね…
- 朝・夜の習慣をメモ、紙などに書き出す
- 作業時間を区切る
- タイマー、スマホのリマインダーなどを活用する
- 「毎日同じ順番・場所・手順で生活する」ように意識する

(管理人)
特に有効なのが「時間を区切ること」です。
物事に「熱中する」と
時間を忘れてしまうのはよくあること。
30分、1時間と最初から決めてしまうことで、
「過集中で疲れる危険性を減らす」ことができます。

(管理人)
習慣は「意思」でなく「構造」で作りましょう。
最初の「作る作業」は大変ですが、
作って、習慣になったあとは、
あなたが心地よくなるように調整すればよいのです。
パニック・不調時の対応マニュアルを作っておく
調子が悪いとき、自分で判断する力も下がっています。
あらかじめ「〇〇になったら、△△する」を決めておくと、
余計なエネルギーを使わずに済みます。

(管理人)
「週末の予定をたてる」ことと同じです。
例:Aに行く➡️ Bで昼ご飯 など…
- 「不調時マニュアル」をスマホ、ノートなどに書く
- 例:ストレス性の頭痛 → カフェイン + 暗い場所 で10分休憩 など
- 情緒不安定 → LINEで信頼できる人に連絡
- 「やらないことリスト」を作る

(管理人)
「やらないことリスト」はおすすめです。
たとえば…
- SNSを見ない
- 電話に出ない
- 朝はスマホを触らない など
作る際は、あなたの直感を信じて作りましょう。
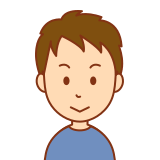
(管理人)
「自分を助ける仕組み」を事前に準備すれば、
思考停止になったとしても、
ダメージを最小限に抑えることができます。
自分の取扱説明書を持ち、更新する
自己理解は、自己管理の基礎です。
「自分がどういうときに困るのか」「何に安心を感じるのか」を整理しておくことで、
トラブルや不調を未然に防げます。

(管理人)
世の中のあらゆるものに、
説明書があることと同じように、
自分だけの「トリセツ」があれば、
困ったときに非常に役に立ちます。
- 「得意・苦手・困りごと」の棚卸しする
- 紙、スマホなどに書き出す
- 相談支援専門員、支援者などと一緒にすると◎
- 一人になる時間をつくる
- そこで、最近の様子を振り返る

「得意・苦手・困りごと」は、他人からよく見えています。
私も就労移行支援の職員さん達に、たくさん教えてもらいました。

(管理人)
自分の取扱説明書は「変化するもの」です。
「定期的な更新」が大切になります。
「すべて一人で抱えない」ことも自己管理
完全な自己完結を目指すと、かえって疲れてしまいます。
必要なときに周囲に頼るのも、立派なセルフマネジメントです。

(管理人)
「他人を頼るなんて怖い」
私にもそう思う時期がありました。
しかし、他人は必要な存在でした。
『人間は一人では生きていけない』のです。
- 信頼できる人と定期的に連絡を取り合う
- 週1の雑談でもOK
- 就労支援・地域のピアサポートを活用する
- 検索すれば、必ずヒットします
- 「自己管理をやめる日」をあらかじめ作っておく

(管理人)
何か困ったことがあれば、上司に報告したり、
主治医、「就労継続支援」の職員さんに話をしています。
「環境が整っているからできること」
そう思われがちですが、
「自分から意見を発信する」ことで
「安心して相談できる環境」を維持しているのだと考えています。
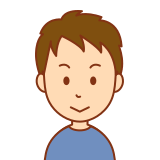
(管理人)
頼ることは「失敗」ではなく「戦略」です。
最初の一歩は非常に怖く、勇気のいることだと思います。
わからなければ、私を頼っていただけると
とても嬉しいです(^^)
おわりに:「管理」とは『あなたを苦しめるものではない』
自己管理という言葉にプレッシャーを感じる必要はありません。

大切なのは、あなた自身の特性に合った仕組みを、
自分で少しずつ作っていくことです。
必要なときに誰かに頼ってもいいし、手を抜く日があってもよいのです。

あなたの「できる」は、あなた自身が一番よく知っているはずです。
もし分からなくなっていたとしても、
信頼できる人や公的機関を利用し、発見してもらえばよいのです。
支援や工夫を取り入れながら、
「自分らしく生きる」ためのセルフマネジメントを、
今日から少しずつ始めてみませんか?







コメント