※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、プロモーションが含まれています

「ASDなそら」管理人のそらです。
ASD(自閉スペクトラム症)当事者の視点で、
仕事・生活に役立つ情報を発信しています(^^)
「精神科」「心療内科」を受診するとき…

どの医者に診てもらえばいいのだろう?
この壁にぶち当たる方は少なくなりません。
身体の病気なら「近所の内科」「専門医のいる大病院」など
比較的選びやすいかもしれません。
しかし心の病気は目に見えにくく、
診断・治療方法も医者によってスタイルが大きく異なります。
一度受診しても…

この医者とは合わないかも…
そう感じることは珍しくありません。

(管理人)
多くの人が最初の段階で違和感を抱き、
悩みながら通院を続けていることと思います…
そんなときに出てくるのが「医者のウィンドウショッピング」、
「ドクターショッピング」という考え方です。
つまり複数の医者を試して、自分に合った主治医を見つけるという方法です。
しかしこの方法には賛否両論があります。
- 賛成派「相性のいい医者に出会うことが、治療の第一歩」
- 反対派「医者を変え続けると、治療が遅れてしまう」
- 管理人の経験談
- それぞれの意見の掘り下げ
- 医者を選ぶときのポイント
- 受診準備
- トラブル対応
- 転院の流れ
私の経験:合わない医者に出会ってしまった

(管理人)
私はこれまでに、
「一回」転院経験があります。
「転院」と呼べるかはさておき…
(このあと理由がわかります)
最初の病院は調べた結果、
「家から近いから」という理由で選びました。
最初の診察では、医者は淡々と質問をして30分が終わりました。
正直に言えば違和感はありませんでした。
ところが、二回目の診察で大きな出来事がありました。
父に付き添ってもらって受診したとき、
医者は私に厳しい口調でこう言いました。
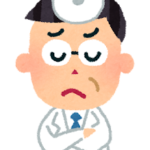
- どうしてそんなことを考えるの?
- 本当にその気持ちがあるの?
まるで尋問のように追い詰められる口調でした。
私はプレッシャーに耐えられず、
その場で号泣してしまいました。

気持ちを理解してもらえるどころか、
否定されたように感じたのです。
おまけに「1時間という診察の長さ」もありました。
次の方も多くいたので、
申し訳ない気持ちになった記憶があります。。。
父も同じく「この先生には任せられない」と感じていたようです。
結果として、その病院に通うのをやめました。
幸い、その後に出会った医者は丁寧に話を聞いてくれる方で、
ようやく安心して通院できるようになりました。
今もそちらに通院しています。

(管理人)
振り返れば…
- この医者じゃなくてもいいんだ
- 私のことを否定する人からは、離れてもいいんだ
そう思えたことが、私にとって大きな転機でした。
もし最初の医者に無理に通い続けていたら、
心療内科そのものに不信感を抱いて、
もう受診できなくなっていたかもしれません。
賛成派:「自分に合う医者を探す」のは「当たり前」
医者によって治療スタイルが違う
精神科・心療内科の医者には、いくつかのスタイルがあります。
- 「薬物療法を重視」する医者
- 「とにかく今のつらさを和らげたい」人向け
- 「カウンセリングを重視」する医者
- 「話を聞いてもらいながら少しずつ整理したい」人向け
- 「生活習慣の改善を重視」する医者
- 「薬にできるだけ頼りたくない」人向け
このように治療方針は大きく異なります。
自分の考え・症状に合ったスタイルを見つけるには、
実際に診てもらわないと分かりません。
「相性のいい医者と出会うこと」が治療の第一歩
精神科の治療は「医者との信頼関係」が最も大切です。
「この先生なら安心して話せる」と思えるかどうかで、
治療の進み方は大きく変わります。
- 通院そのものが、苦痛になる
- 薬も飲みたくなくなる
- 結果的に、治療そのものを放棄してしまうリスクがある

(管理人)
複数の医者を試してでも
「安心して任せられる医者を探す」ことは
意味のある選択だと思います。
反対派:ドクターショッピングには「デメリットもある」
治療の一貫性が失われる
精神科の治療は継続性が重要です。
薬の効果が出るまで数週間かかることもあり、
医者を変えてしまうと、その調整がゼロからやり直しになります。
結果的に「どの医者でも中途半端」という状態に陥る危険があります。

信頼関係が築きにくい
医者の立場からすれば、患者が短期間で医者を変えていると
「この人は本気で治療を受けたいのだろうか?」と思うかもしれません。
「治療はお互いの信頼で成り立つ」ので、
短期間で転院を繰り返すと不利になることがあります。
「同じ医師に」「診てもらい続ける」ことに「大きな意味」があります。

(管理人)
表面のことしか分からず、
根本的な原因を取り除けなくなってしまうのです…
「完璧な医者」はいない
どんな医者にも長所/短所があります。
「100%自分に合う医者」を探し続けると、
永遠に治療が始まらない可能性があります。
ある程度の「許容ライン」を決めることも必要です。

医者を選ぶときの「実践的なポイント」
では、どうやって医者を選べばよいのでしょうか?
- 最初の3回で見極める
- 1回では判断できない
- 「安心できるか」「話を聞いてもらえているか」を基準に判断する
- 事前に情報を集める
- 「口コミ」「病院HP」「治療方針」を確認する
- カウンセリングに力を入れているか、薬物療法中心かを調べる
- 診察中にチェックするポイント
- 「話を遮らず」聞いてくれるか
- 「質問に対して」説明があるか
- 「薬の効果」「副作用」について説明があるか
- 薬剤師についても、同じことが言える
- 「家族」「生活面の相談」にも対応してくれるか
- 家族の同行を検討する
- 家族の視点もあると医者に伝わりやすい
- 関係が悪い場合は、無理にする必要はない
- セカンドオピニオンの位置づけ
- 転院ではない「別の視点を聞くため」として利用するのも有効
受診の準備:「症状メモ」「質問リスト」
初めての受診では緊張して、言いたいことを忘れてしまう人が多いです。
そのため、事前に準備しておくと安心です。

(管理人)
私は定期通院の前に、いつもメモを準備しています。
症状メモの作り方
- いつから調子が悪いか
- 例:1か月前から眠れない など
- どんな症状があるか
- 例:動悸、頭痛、気分の落ち込み など
- 生活への影響
- 例:仕事に集中できない、人と話すのがつらい など
- 過去に試した対処法(特に初診)
- 例:市販薬、運動、休養 など

(管理人)
できる限り「詳しく伝える」のがよいです。
たとえば…
- 天気が悪い日は朝から頭痛がする
- 家族と一緒にいると気分が落ち込む など
メモを作っているときは苦しく感じるかもしれませんが、
受診するとスッキリできますよ(*^^*)
質問リストの例
- この症状は病気の可能性があるのか?
- 薬はどんな効果と副作用があるのか?
- 治療の目安はどのくらいか?
- カウンセリング、リハビリは受けられるか?
紙・スマホに書いて持っていくだけで、診察が格段にスムーズになります。
「メモの実物」を公開
以下に、私が実際に記したメモを公開します。
参考にされてください(*^^*)
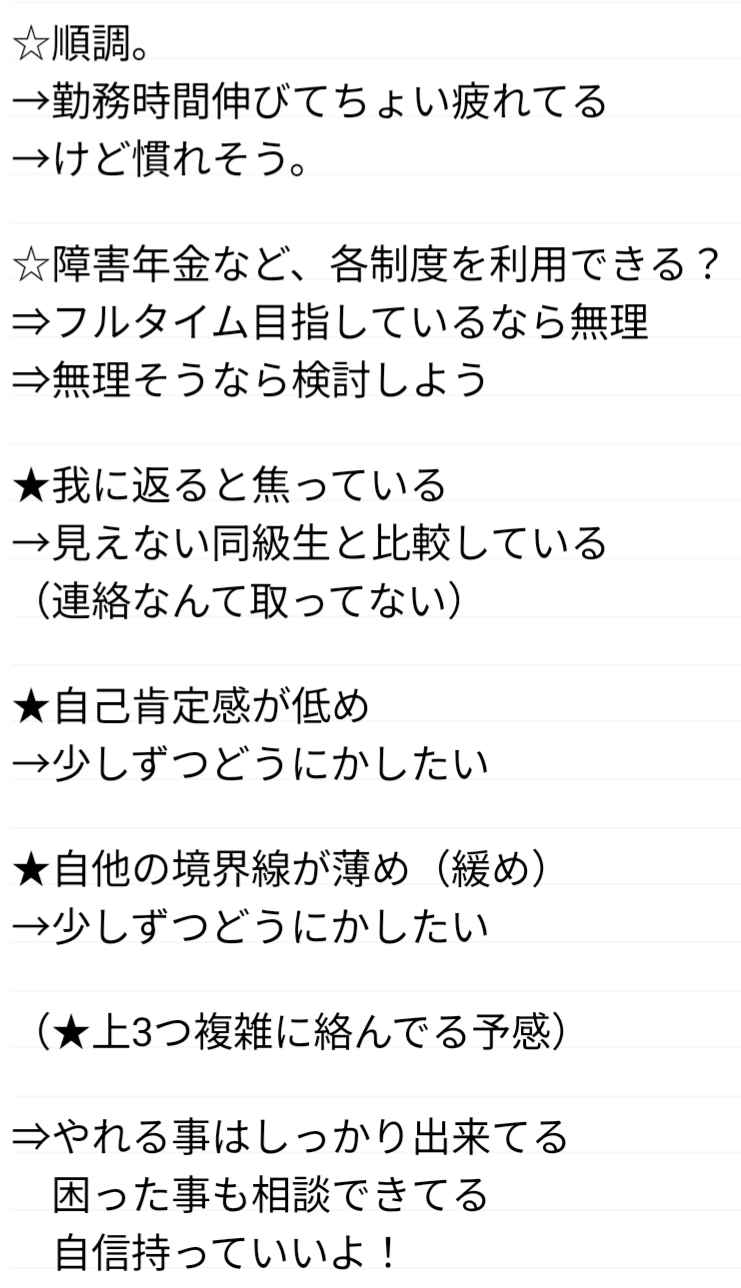
マークについて説明
- 「☆」ポジティブな出来事
- 「★」ネガティブな出来事
- 「→」自分の考え
- 「⇒」主治医の考え(診察中に追記)
医者とのトラブル:「相談」として伝える
ときには医者の対応に違和感を覚えることがあります。
そのとき大切なのは「感情的にぶつけない」ことです。
- 「クレーム」ではなく「相談」として話す
- 「私はこう感じました」と主語を自分にする
たとえば…
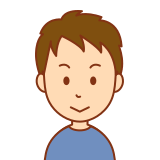
先生のお話が少し早くて、ついていけませんでした。
もう一度ゆっくり説明していただけますか?
このように伝えると、医者も受け止めやすくなります。
それでも改善されない場合は、転院を検討してよいでしょう。

(管理人)
気持ちが沈んでいるときほど、
ぶつかりたくなる気持ちもわかります。
この時、丁寧に話を聞いてくれる
医師と出会えると良いですね(*^^*)
医者を変えるとき:「紹介状」と「薬の継続」
もし転院を決めたら、スムーズに切り替えるために準備が必要です。
- 新しい病院でスムーズに診てもらうために有効
- 医療情報が記載される
- 診断名、処方内容 など
- 必須ではない
- あった方が安心
- 途中で薬が切れると体調が悪化する可能性がある
- 転院前に「○週間分処方してほしい」とお願いしておくと安心
- 「今の先生が悪い」ではない
- 「自分に合う先生を探すため」と考える
- 医療機関にとって転院は珍しいことではない
- 「申し訳ないな…」など、気負う必要はない

(管理人)
もし転院されるときは、
「時間の余裕を持ってする」ことをおすすめします。
「紹介状」は「診断書」と同じく
「医師が時間を使って書き記すもの」です。
「今日ください」は避けましょう。
「障害」「精神疾患ごと」の視点

(管理人)
主な症状を取り上げてみます。
ASDの場合
- 医者と「話し方の相性」が重要
- 言葉のニュアンスに敏感
- 医者が「一貫した説明」をしてくれるか
- 決まった手順が安心

(管理人)
私は「事実を淡々と述べてくれる」が大切と考えています。
分かりづらい説明をされても、聞き返すだけなので(・_・;)
うつ病の場合
- 「家族」「支援者」の協力が大事
- 判断力が低下しているため
- 薬の効果、副作用の説明が丁寧な医者が信頼できる

「うつ病」に限らず、協力者はいることが望ましいです。
ただし、根本的な原因が同居している家族にある場合、
いなくても大丈夫です。
医師と二人三脚でしっかり治療していきましょう(^^)
パニック障がいの場合
- 具体的なアドバイスしてくれる医者が望ましい
- 発作が起きたときの対応 など
- 「気のせい」と軽視する医者は避ける

(管理人)
「病は気から」
この言葉を使ってしまう医者も残念ながらいます。
私の経験上、さっさと次を探すのがよいです…
おわりに:「あなたにとって」ベストな医者とは?
✅ 医者によって治療スタイルが違う
✅ 信頼できる医者を探すのは当然
✅ 相性の良い医者に早く出会えば、治療がスムーズに進む
❌ 医者を変えすぎると治療が中途半端になる
❌ 完璧な医者を探し続けると治療が始まらない
- 受診準備
- 症状メモ、質問リスト
- トラブルは「相談」として伝える工夫
- 転院時の紹介状、薬の確保
これらを意識することで、安心して治療を続けることができます。
あなたはどう思いますか?
「最初の医者にそのまま通い続ける?」
「納得できる医者が見つかるまで探す?」
ぜひ、あなたの経験・考えに照らし合わせて考えてみてください。

(管理人)



コメント