※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、プロモーションが含まれています

「ASDなそら」管理人のそらです。
ASD(自閉スペクトラム症)当事者の視点で、
仕事・生活に役立つ情報を発信しています(^^)
- スマホが突然鳴ると、体が固まってしまう
- 家の固定電話が鳴ると、心臓がバクバクする
- 非通知なら最悪…
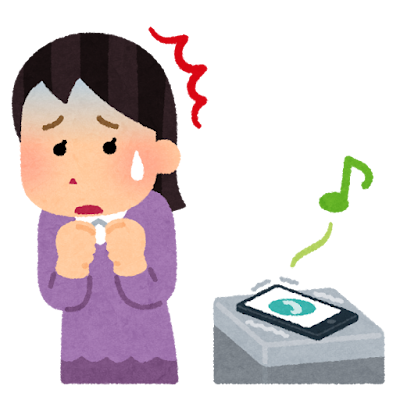
もしあなたが、この記事を読んでいて「あるある」と思ったなら、
きっと私と同じように「電話が苦手」なタイプかもしれません。

(管理人)
私はASDの特性があり、昔から電話が大の苦手でした…
でも「目標」を決め、「練習」を重ねたこときっかけに、
その苦手意識が少しずつ和らいできました。
この記事では、電話がなぜ苦手なのか、そしてどう向き合ってきたか、
ASD当事者である私の実体験を交えてお伝えします。
なぜ「電話がこんなにも苦手」なのか?
電話が苦手な理由は、人によってさまざまですが、
私の場合はいくつかのポイントがありました。
① 突然の着信音に強いストレスを感じる

(管理人)
私は昔から、
電子音・大きな音に過敏なタイプでした。
- 黒板を爪でひっかく音
- 金属がこすれる音 など
「ゾワッ」とする音がとても苦手です。
電話の呼び出し音も、
それと似た感覚を引き起こします。
特に自宅の固定電話は、音が大きく設定されていることが多く、
突然鳴るとドキッとします。
スマホの着信音は無音に変えていますが、
それでも「予期せぬ音」は心の準備ができていないため、
どうしても緊張してしまいます。
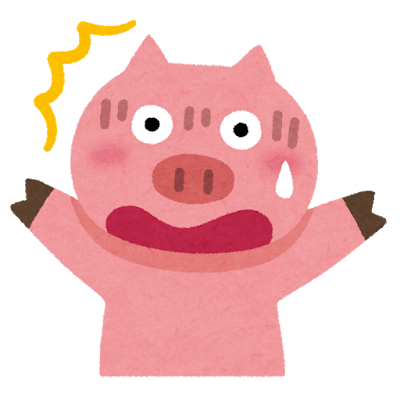
② 相手の表情が見えない = 情報が不足する
ASDの特性として、「非言語コミュニケーション(表情・ジェスチャー)」に
強く依存する傾向があります。
つまり言葉の裏にある「気持ち」や「ニュアンス」を読み取るためには、
視覚的な情報が重要なのです。
電話では、その55%以上の情報がまるっと欠けてしまう。
これは、私にとってかなりのストレスです。
「今の沈黙は怒ってる?」
「語尾が強かったけど、どういう意味だろう…?」

(管理人)
このように、不安がどんどん膨らんで、
通話が終わったあとも
気持ちがざわざわしてしまうことが
よくありました。
③ 相手の反応がわからず、自分の伝え方にも自信が持てない
私にとって「ちゃんと伝わっているか」が確認できないのが、
大きな不安要素でした。
- 対面 ➡️ 「相手のうなずき」「表情」で理解度がわかる
- 電話 ➡️ 「うなずき」「表情」が分からない

(管理人)
「声のトーン」「返事の速さ」『だけ』で
判断しなければならないのは、
正直しんどいです。

それでも「少しずつ向き合えた」理由
電話克服のきっかけは「事務職に就きたい」という目標から
私が電話に少しずつ慣れるきっかけになったのは
「事務職に就きたい」という強い思いからでした。
事務職では、電話応対が避けられない場面もあるからです。
そこで私は、電話の苦手意識を
少しでも和らげたいと考えるようになりました。

就労移行支援での「練習体験」
就労移行支援を利用していた頃、
職員さんと一緒に電話練習をすることになりました。

(管理人)
詳しく説明すると、こうなります⬇️
- 退勤後にする
- 「自宅へ帰った」ことを報告するだけ
- 数日に分けて、行う

回数は多くはありませんでしたが、
その都度、受け答えの様子を細かく確認されました。

(管理人)
振り返りでは、
「受け答えも落ち着いていて、問題なくできている」
そう言われ、自分でも驚きました。
「電話の内容」「会話自体」は、苦手ではない。
私にとって強いストレスになっているものは ⬇️
- 固定電話の着信音の「刺激の強さ」
- 非通知の着信に対する「不安感」
つまり ⬇️
- 「着信音」「非通知の不意打ち」さえなければOK
- 電話応対自体、それほど苦ではない
- 「電話」より「メール」が、より得意
- 情報の聞き取りミスを、防ぐことができる

「 電話が苦手 = ダメ 」ではない
電話が苦手ということは、逆に言えば
「他のコミュニケーション手段のほうが向いている」という証拠でもあります。

(管理人)
先ほど紹介した通り、
私自身「電話」よりも
「メール」「チャット」の方が得意です。
なぜなら以下の点が、自分の特性に合っているからです。
- 情報の聞き漏れが起きにくい
- 誤解が起こりにくい
- 記録が残る
電話に苦手意識があるからといって、自分を責める必要はありません。
むしろ、自分に合ったやり方を選べる柔軟性があるということを誇っていいのです。

電話が苦手な人の「現実的な対処法」
ここからは、
私自身が実践してきた&効果があった方法をいくつか紹介します。
①「対面がいいです」と素直に伝える
たとえば、職場でのやり取り・人間関係において、
「対面でのコミュニケーションが助かります」と伝えるのは全然アリです。
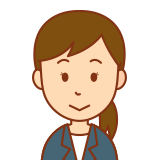
- 図・資料を見ながらだと、理解しやすいです
- 相手の表情が見えると、安心できます
そういった理由を添えれば、ほとんどの人は納得してくれます。

(管理人)
納得してもらえない場合、
他の方に相談しましょう。

② 「メール」「チャット」を優先する
仕事やプライベートでも、
できるだけ「文字ベース」のやりとりを選びましょう。
- 記録が残る
- 返信を落ち着いて考えられる
- 誤解を避けやすい

(管理人)
私も仕事の連絡は、
可能な限りメールでお願いしています。
「口頭だけで説明されるより、正確に伝えられるから」
そう伝えると、理解されやすいです。
③ 家族・親しい人には「電話を控えて」とお願いする
自宅の固定電話に関して、
私は家族に「できればLINEで連絡して」とお願いしています。
最初は「なんで?」と聞かれましたが、
「電話は苦手だから」と理由を伝えたら、理解してくれました。

「就活」で「電話が苦手」と伝えるときのポイント
もし就職活動中で、「電話が苦手なこと」を伝える必要がある場合、
以下のように具体的に説明すると好印象です。
| NG例 ❌️ | OK例 ⭕️ |
|---|---|
| 電話は苦手です。 | 突然の音に過敏でパニックになるため、 電話は難しいです。 代わりに、メール等なら正確に対応できます。 |
| これだけでは「誤解されがち」 | 「代替手段がある」ことを伝えると、 前向きな印象を持たれやすくなります。 |
おわりに;苦手を「個性」に変えていく視点を
電話が苦手だと、「社会に出てから困るのでは?」と
不安になる人も多いと思います。
今はコミュニケーション手段が多様化しており、
電話以外の手段も十分に通用します。
- 電話が苦手なら、他の手段を磨けばいい
- 自分が安心して話せる環境を選べばいい
- 苦手なことを無理に克服しなくても、生きていける
これは私が、就労移行支援や実体験の中で学んできたことです。
電話が苦手でも、自分なりの方法で社会とつながることは可能です。
そして、そういった方法を「自分らしさ」として堂々と選べるようになることが、
ASD当事者の私たちにとっての「生きやすさ」なのではないでしょうか。

(管理人)
質問などあれば、お気軽にコメントしてくださいね。
Xでもお待ちしております(^^)



コメント