※本サイトで紹介している商品・サービス等の外部リンクには、プロモーションが含まれています

「ASDなそら」管理人のそらです。
ASD(自閉スペクトラム症)当事者の視点で、
仕事・生活に役立つ情報を発信しています(^^)
この記事では、中学生のときのお話をしています。
部活開始、しかしー
中学校に入ると部活加入を「半」強制されます。
当時の友人の一人は入っていなかった記憶はありますが…
それでも「入った方がいい」という色々な方向から聞き、運動部に入りました。
その中でも卓球を選択しました。
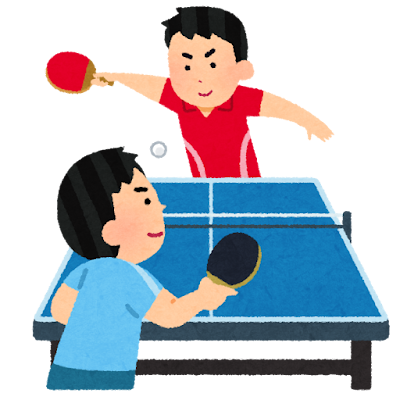
- 屋内 → 屋外だと暑い
- 楽しそう → 厳しい部活は嫌
実は自分は、球技は得意ではありません。
小学校の球技大会にて、ソフトボールは参加しませんでした。
「やる」よりも「見る」ほうが好きなのです。
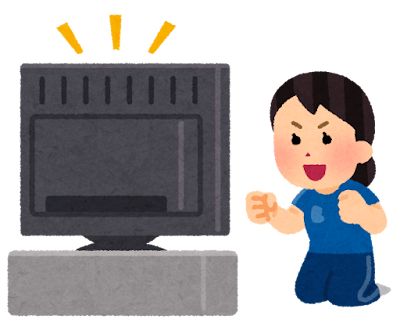
それでも入部することになったのは「入った方がいい」という大人の声。
そしてほとんどの人は入っていく、という事実。
当時は自分の意志で決断できませんでした。
その結果周りに流される結果となりました。

しかし入部したら楽しかったです。
顧問の先生が時に厳しく、時にゆるく指導してくださりました。
同級生も上級生も、下級生とも仲が良かった記憶があります。
望外だったのは、痩せたことでした。
小学校の卒業写真は、ふっくらしていましたが、
ものの1年で「シュッとした印象」に変わりました。
数学そのものは好き、授業は嫌い
中学校に上がると算数から数学に変わります。
今思えば一体何が変わった、というのでしょうか…
気になったため調べてみると、下記のように違いがありました。
「算数」「数学」の違い(気になる方は、ご覧ください)
算数と数学の違いは、解答とプロセスのどちらを重視するかでしょう。
算数は実用的な計算で正確な答えを導き出すことが目的で、
数学は「なぜそうなるのか」を数字や記号を用いて、
論理的に説明することが目的になります。
例えば、算数は個数や距離など具体的な場面が想定されていて、
計算や算数の力を使って答えを出すといった内容です。
一方で数学は、証明問題など、答えよりも数学の世界のルールを知って、
ルール通りに進んで答えにたどり着く過程を重視する内容になっています。https://www.edic.jp/column/article/16.htmlより
「1つの解答よりも、プロセスを重視する」
それを強く感じたのは、中学3年間を通じて教えてくれた数学の先生です。
それは「結果ではなく過程が大事である」ということです。
言葉だと分かりづらいため、実例をもとに紹介します。
「2x+3=13」 を解け.
わかった!「x=5」だ!
その先生は「そうではない」と何度も繰り返し言っていました.
2x+3=13
2x=13-3
2x=10
x=10/2
x=5
- 両辺から3を引く.
- 両辺を2で割る.
これらの過程こそ大事であるー
パッと見てすぐ解ける問題も過程をしっかり記しなさいー
こう教えてくれたのです.
結果こそ全て、というこの世界ですが
過程をより大事にしたいーそう思うきっかけとなりました。
そして、もう一つ考えるきっかけを与えてくれました。
「とある問題を間違えた。次に同じような問題が出てきた時どうするか?」
「ミスをした。次に同じようなミスをしないために何ができるか?」とも言えるでしょう。
一人でもできますが、複数人でするほうが良いです。
しかし人数を増やしすぎてもいけません。
このバランスは人によって異なると思います。
「いじり」という名の「いじめ」
中学1・2年生の時にいじめを受けていました。
自分はどこか周りから浮いていたのでしょうか…
いじめられる側は「どうして自分がこんな目に…?」が分かりません。
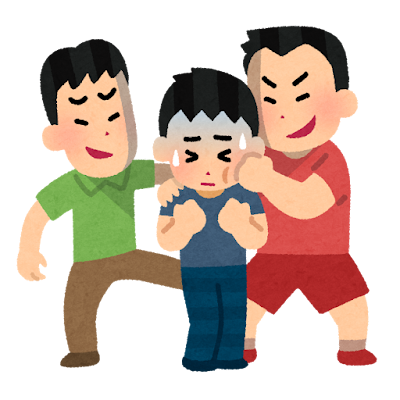
いじめた側は「いじる」程度でやっていたのだと思います.
- トイレに入ると、上からこそっと見ていたり…
- こけさせようとして、足を出してたり…
やってくる事を予測して、全力で逃げた事もありました。
偶然、担任の先生に見つかり、難を逃れる事ができました。
そして当時の担任の先生などのサポートもあって、
通学は継続することができました。
私はいじめられている事は、心に傷を負いましたが、
周りの目は気にしていませんでした。
また3年生のときは、いじめた側の人と一緒のクラスではありませんでした。
ある意味助かった…ところです。
遊びまくり、ではないけど…
友人関係が一気に広がったのは中学生の時です。
その始まりとなったのはカードゲーム、
そのなかでも「遊戯王」です。
小学生当時もやってはいたのですが、
桃鉄を遊んでいた友達としか遊んでいませんでした。
その友達が同じ部活の友達を紹介してくれるようになりました。
そこから遊ぶ友達が増えていきます。
- お家に上がらせてもらったり
- 近所のカードショップで遊んだり
平日のみならず休日もよく外出するようになりました。
ゲームにおいても自分は本気でした。
「勝ちたいー」
負けると悔しくて、どうやったら勝てるのかをよく深く考えていました。
手元のカードを上手に使って勝てないか、真剣に考えていました。
この時期も幼稚園の時から同じく「広く浅い」人間関係でした。
そのため、「しょっちゅう会うけどよく分からないなぁ…」という方もいました。
現在につながる出会い
中学生の時、今につながる出来事がありました.
それが「障がい者の方と友達になった」事です。
同じ部活の同級生に、障がいを抱えている方がいました。
補聴器をつけて、専用の道具を使って先生の話を聞くー
変わった話し方をするなぁ…と感じていました。
いじり合ったり、深い話をしたりしていると、
「どこか波長が合うなぁ…」と感じていました。
障がいを持つ者同士、どこかしらリズムが合っていたのでしょう.
今会う機会があるのなら、どのような障害を持っているのか気になります。

また3年生の時に、幼稚園や小学校の時にいた方が、
同じクラスに転校してきました。
どこから来たのかな、と当時思いましたがおそらく特別支援学校でしょう。
その方も話し方が独特で、時に変な行動を取っていました。
それでも修学旅行の際は、
先程の障がい者の方(補聴器をつけた方)と一緒の班で行動しました。
その時自分はリーダーを務めましたが、よくやりきったな…と思っています。
「挑戦する気持ち」を信じた高校受験
高校受験の時期に差し掛かったとき、以下の選択肢がありました。
- 「中」の公立高校に行く
- 「上」の公立高校に行く
- 「中〜上」の私立高校に行く
結果から言うと「2」と「3」を取りました.
きちんとオープンスクールに参加し、どんな場所か、
どんな授業があるかを確認した上で、3つの選択肢に絞りました。
私立に関して、小学校から習っていた英語を、
更に使いたいという事で1校に絞っていました。
公立に関しては「チャレンジしたい」
この気持ちが全てでした。
その気持ちを両親と担任の先生は尊重してくれました。
実は校区外にも行ってみたい公立高校がありました。
ただし「下宿しないといけない」という点から断念しました。
引っ越すという手は、家族内でも出てきませんでした。
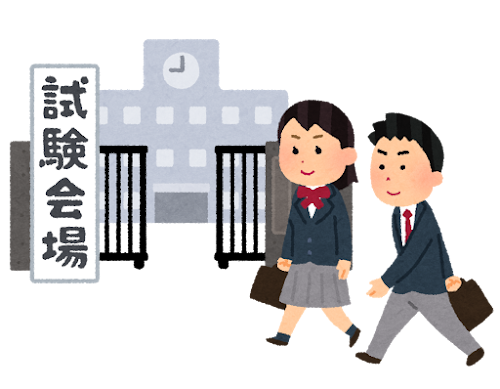
私立高校には順調に合格し、公立高校の受験を終え合格発表へー
当時は現地に赴き、合格発表を見る形だったので緊張しました。

結果は合格。
公立高校に進む事を決断しました.
しかし同じ中学校から進学するのは10人にも満たず、かなり不安でした。
友人を作る事は幼稚園の時から苦手だったためです。
鋭意、執筆中です…(_ _)
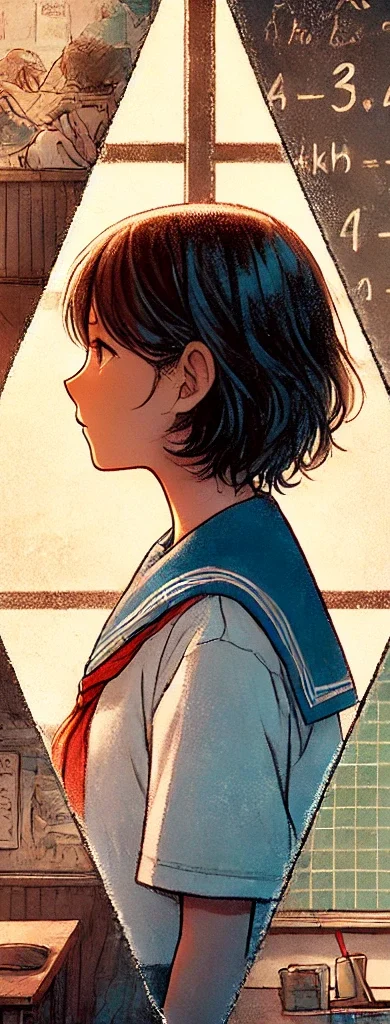


コメント